転職したこと、観た映画のこと
転職
先日近況報告で述べたとおり転職することにしました。次は出版社で、編集者として働きます。このブログでは時折学校や教育の話をしてきました。書き手である私が学校の先生であるように書いた記事もいくつかありますが、それらは現実に近いフィクションで、これまでの仕事は教職というわけではありませんでした。(とはいえ、そうした記事の内容は現実にあったことに根を持っているので「噓」ではありません。)
他方で次の仕事が編集者であるということは事実です。何にまれ、読むこと書くことに関わった仕事をしたいという気持ちから、この道を選択しました。誰かの想像力が社会に分有されることに一役買いたいなと思います。
人生で何をどうしたいのかいまだにわかりませんが、都度「こっちの方かな?」と思える道を、仔細に検討した上で選択し、とにもかくにもできることをしていった軌跡を、最終的に回答として差し出せば、「お前はこの人生で何をしてきたのか」と恐らく一番厳しく問うであろう晩年の自分も、不承不承納得してくれるのではないだろうか、と考えます。編集業務は未経験なので今年一年は大変かもしれませんが、まずは前だけを向いて頑張ります。応援してくれた皆さんありがとうございました。
デジモンアドベンチャーlast evolution 絆 を観た。
酷かった。太一とヤマトが空っぽすぎて辛かった。どうしてこうなったのか。デジタル上のモンスターとそれを育成する子供との関わりというデジモンの主題は深められず。これが「ラスト」なのであればあまりに貧しい。
河童のクゥと夏休み を観た。
非常にすけべな映画だと思った。中年男性達が「少年」という表象に対して持つ欲望がはしたなく開陳されている。一種のポルノグラフィ。しかし、欲望の貫徹は評価したい。
ポケモン剣盾に対して持ってしまう違和感:ジムリーダーが本当に強くはならないか
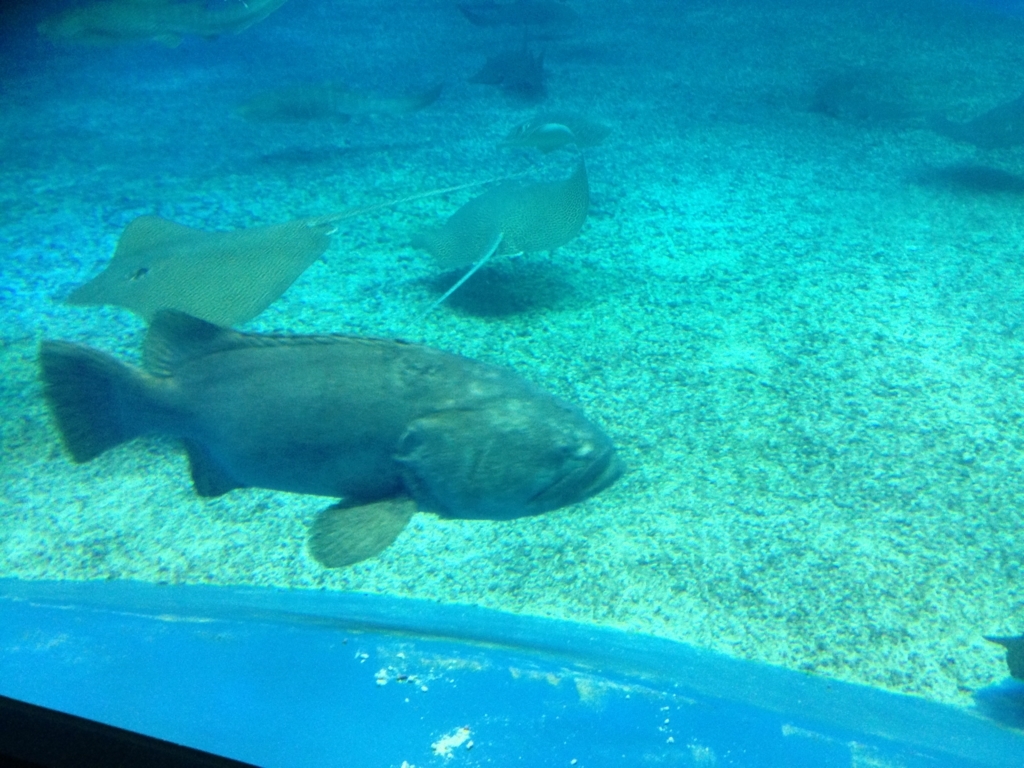
言わずと知れたポケモンの最新作ソード・シールド。昨年(2019年)11月の発売後は、コアで辛口な有象無象のファン達からも概ね高評価を持って受け入れられ、シリーズ中の佳作としての評価は定着しつつあります。実は私はゲームのプレイ動画をちょくちょく見るのですが、今作については、見る中でずっと前からポケモンに持っていた違和感を改めて感じることになりました。今回はそれについて。ちなみに大前提としては、今作を私も高く評価しています。
第一世代からフォローしています
ポケモンゲームをプレイしたのは中学時代のルビー・サファイア(2002年)が最後ですが、以降のシリーズについてもプレイ動画はここ二年くらいですべての分フォローしてきました。世界観、キャラクタ造形、対戦システムなどがいずれも幼稚園児だった頃にプレーした第一世代(赤・緑・青)よりはるかに洗練されてきていることは論を待ちません。対象年齢は低めな気はするけれど、第一級のコンテンツであることは疑う余地がないと思います。
しかし、プレイヤーとして第一世代を遊んだ幼稚園の頃から長らく感じていた違和感は結局解消されていません。だから駄目だというつもりはないし、むしろそれは、プレイヤーを後述するように映画・アニメなどの派生コンテンツに向かわしめるようなゲームの魅力とも捉え直せる気はしますが、ともかくどんな違和感なのかについてまずは書きます。
勝負の論理と人―ポケモン関係との間の溝
簡単に言えば、プレイヤーが持つポケモンへの愛着が戦闘では単に数値や相性の勝負に還元されてしまうことが私にとっては違和感を感じるポイントです。
ポケモンの世界では、パーティーとしての強弱を度外視して、ポケモンと付き合う人々が現れます。典型的なのはジムリーダー。勝負に勝つためには多様なタイプを手持ちに入れていたほうが圧倒的に有利ではあるのに、彼らは水なら水、という形でタイプをそろえる。風貌もタイプイメージにそろえている。彼らはどのようなポケモンを有しているかがアイデンティティと分かちがたくなっているトレーナーです。
それらが弱いトレーナーではなく、むしろ強者=ジムリーダー、四天王として立ちはだかるのは、多様なタイプを手持ちにしているほうが戦闘には有利という勝負の論理には反しています。しかし彼らは勝負の世界で強いことになっている。この矛盾が子供心には違和感として残りました。
ジムリーダーとポケモンとの間にある、魅力的な空白
例えばタイプ相性がよいポケモンを出すことで、レベルが少し高めのジムリーダーの手持ちを何匹も連続でなぎ倒す、というのはよくやられています。プレイ動画を見るたび、大げさに言えば胸が痛みます。
胸が痛むというのはどういうことか。大抵ジムリーダーが出すのはその段階でプレイヤーが目にしていなかったような風貌や技・特性を持っている花形ポケモンであり、演出上作り手が特に重要視しているはずのもの。しかし、タイプ相性が良ければいとも簡単に倒せてしまう。ジムリーダーが満を持して繰り出すポケモンとリーダー自身とのかかわりあいや、リーダーが特定タイプに手持ちを統一しようとするに至るまでの物語は、多くの場合語られないけれども、対戦の裏にはあるはずであり、明示されずともプレーヤーは、それを想像することによってゲームプレイを立体的なものにしていけるはずなのに、そうしたゲームのはらむ魅力的な空白は、タイプ相性のいいポケモンにジムリーダーのポケモンがなぎたおされていくなかで押しつぶされてしまうような気がします。そういう意味で胸が痛いです。
また、制作目線で見ても、お金も時間も膨大に投入されているはず(私の勝手な予想でしょうか)のジムリーダー戦・四天王戦が単純に超えられてしまう仕組み(プレイヤーとしてやって見ればまた違うのでしょうか)になってしまっているのは(胸ならずとも)頭が痛いのではないのでしょうか。
派生コンテンツでやるべき?
ところで、プレイヤーの個人史と不可分なポケモンの選好と勝負における強さとの関係づけの描出までゲームでカバーするべきなのか、という疑問は出てしかるべきでしょう。ルールがあり、そのルールの枠内では何事も可能というのがゲームというものの本性で、それがいいところです。あなたの考えているようなことはアニメ・映画・漫画など感情的機微を描きやすい派生コンテンツを通じて示されるべきだ、というのならそれはそのとおりです。
実際、ここで問題にしている点を含め、ゲームの世界では描き切れない世界設定上の魅力は映画やアニメにより描き出されてきました。
例えば『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』(1998)など大人になった今、「案外安っぽいところがあるなあ」と感じてしまいはするものの、他方で見るとどうしてもどこかで首のあたりがぞわぞわするような、おののきと一体になった感動が這い登ってきます。ゲームの世界観に可能性として内在していたもの―それはプレイヤーとしてゲームに没入する中で自分の中に取り込んでしまった想像力の芽でもある―がはっきりと形を成していると思いました。
ゲームがゲームボーイの中だけのものでなくなったと気づくことは、それに自分自身が接続しうること、すなわち、そのゲームが自分の一部として息づき得ることを感得することと並行していました。作品はいかにして単体の作品を超え出ていくのか、もちろんその頃はそんな風には言語化できなかったけれど、それを目の当たりにできた私にとっての初めての体験。小林幸子の歌う「風と一緒にどこまでゆくの」という歌詞は、ポケモンに自分の一部を持っていかれてしまっていた当時の自分の感覚を代弁していたような気がします(もう憑き物が落ちて久しいけれど、それから20年経ってもこんな記事を書いている)。
制作サイドを応援しています
自分の持っている問題意識はゲーム外で実現されるべきかもしれないとわかっているのなら、なぜわざわざこうしてブログに書く/いてしまうのか。端的に、私が今のゲームの変化についていけていないからなのかもしれません。子供のころに予期していた以上にゲームシステムが複雑化し、グラフィックも精緻になったことから、それを映画か何かのように体験してしまっているのかもしれない。これだけのことができるのだから、例えば水タイプだけのパーティー、ないしはあるプレーヤーが愛着を持ち、長い時間をかけて育てたポケモンが、種族値や相性で負けているポケモンを凌駕するような形のルールに変えていけるのではないか。と思ってしまいます。ただ、まあ、ないものねだりといったらそれまで。
付言しておけば、見たことのないタイプの組み合わせのポケモンが多数出現し、タイプ相性を判定することが難しくなっていたり、なつき度と連関したわざが現れたり、雨パや晴れパといった似通ったタイプを揃えることで有利になる戦略が可能になったりと対戦がこれまでそうだったような形の単純な数値争いに還元されないような方向に開かれつつあることは重々承知です。ジムリーダーが戦闘中に話しかけてくる演出も、ジムリーダーの中の物語を想像するよすがになっており、制作サイドが如上のように感じるプレイヤーに応答しようとしていることもよくわかっています。なので、応援したい。
最後に。もしポケモンが今ひとたび、育成バトルRPGゲーム史を塗り替える圧倒的な進化を志向するのだとしたら、その可能性の一つは、プレーヤーがポケモンに対して持つ愛着を今まで以上に対戦システムと関連させるにはどうするかということを考える方向の中にあるのではないかと思います。
思春期の性と身体をどう文学に描くか:村田沙耶香『しろいろの街の、その骨の体温の』

先日書いた近況報告のエントリで最近全然本が読めていないと書きました。今読むと、このエントリは一つの記事としてはあんまり長大で読みにくい部分があるのでそのうち分けるかもしれません。
そんな中でもしっかり読んだものが全くないかといえばそうでもなく、標題に掲げた村田沙耶香の作品を紹介したいと思います。
これまで思春期の性と身体を描いた現代文学の作品でピンと来るものに出会えてきませんでした。あるものは登場人物があまりに自意識過剰かつ自罰的で乗れず、あるものは対照的に極めて放埓で不埒なため、読み進めることが難しかったです。極端な方向に陥りやすい時期であることはわかりつつ、極端なものを極端なまま書くことでは文学として自立していると言えるか怪しいのではないか、でもどうやって書けばよく書けていると言えるんだろう、とぼんやり考えつつ答えは出ていませんでした。
本作はそうした問いに一つの答えを提示したこのジャンルの白眉だと思います。
概略
この作品については以前このブログでも触れました。
その時に書いていたことを少し引いてみると
最近珍しいニュータウンを舞台にした小説。ニュータウンの開発やその停滞と第二次性徴期の身体の変化とを重ね合わせて書くのが小説の基本的な仕掛けで、その上にカースト間の対立厳しい教室で生きる様々な層の生徒たちの生きざまとその裏にある不安や葛藤が、主にカースト下位の私の自己防衛的観察眼により剔出される。
はいそうでした。スポーツ万能でクラスの人気者である、淳良そのものな伊吹が自分の顔貌にコンプレックスを抱える陰気な「私」こと谷沢という女子に小学校の時の関係の延長上で何度もキスを強要されるという筋書きは、それだけ聞くと本当に小説として立ち上がるのか不安になりますが、スクールカーストの問題をかませながら見事にまとめられています。
身体を通じた世界との新たな出会い
で、今回再読して気になったのは、性徴が発現する時期の身体との関わり方をどう書くかということ。『地球星人』(2018年)もそうでしたが、村田さんは自慰や性行為を割とストレートに神秘的なものとして描きます。以下は「私」(谷沢)の自慰のシーン。
ふと、窓ガラスに映った自分を見た。交尾した蝶々の羽のように、またはあのとき唇の中で震えた伊吹の性器のように、自分の肉体も、神秘的な振動を繰り返していた。
[中略]
伊吹の、あのとき聞いた、小さな悲鳴のような呼吸が耳に蘇った。そのときの濡れた目と、舌にひろがる体温を思い出した瞬間、爪先からぴりっと、小さな、光の粒でできた雷のようなものが走って、脚の間からその光の粒子がゆっくりと抜けて行った。
私は起き上がり、自分の脚の間を見てみた。何かが抜けて行った感覚があったので、伊吹の精液のようなものか、もしくは何かきらきらした星屑のようなものが、ベッドの上に散らばっていないかと思ったのだ。
(248頁)
「神秘的な振動」「光の粒でできた雷のようなもの」「きらきらした星屑のようなもの」という表現が目を引きます。自慰は①自分の欲望を解消するための恥ずかしい行為で隠匿すべきものとみなされる向きが多いのですが、ここでは②自分の身体の自分ならざる側面との出会いとして語られているように思います。
思春期の性徴が発現する身体はそれまでの身体と異なり個人の力で抑えることの難しいような欲望の発信源となります。①のような自慰の語り方は、そうした欲望を抑え込むべきものとしてみなすことを前提にしており、村田さんの②のような語り方はそうした欲望を新たなものと出会うための一つの経路として捉えているように思います。
「雷」「星屑」とあるように、そうした欲望は自分の身体に対して本来外にあるような自然の諸物とつながっています。『生命式』(2019年)の「街をたべる」などにも見られますが、村田さんは人間の営みを広く自然や生命活動の一部と相対化して捉えることによって、それを新たな角度から活写することを得意としています。ここにもそうした、社会で言説化されてしまった性のありようを改めて外界との関わりから位置付け直そうとする意思が読み取れます。
自分そのものであり、したがってその機構については既にあらかた知り尽くしている身体が知らず知らずのうちに新たな形へと組み替えられる時、組み替わった身体は世界との新しい関係の中に置かれることになる。そして、新たな身体を通してしか垣間見ることのできない、相貌を異にして現れる世界が個を超えたもの=神秘的なものとして経験される。
「恋愛」というのはあまりに毒の回った言葉で使った瞬間に色々嘘を抱え込むことになるので、便宜的に「他者の身体の希求」(小説中の言葉でいえば「疼き」?)と言い換えるのだとすれば、それは如上のように自分の身体と世界との新たな出会いを根本的なところで駆動させるものなのだなと思いました。
うーん、やっと「恋愛」の良さがわかったかもしれないぞ。でもこのように「他者の身体の希求」として「恋愛」を捉えるのだとすれば、やっぱり恋愛には相手の身体に対する欲望が必須ということになるのでしょうか。村田さんの小説を読む限り、それはイエスに見えます。直観にも一致。
自己から他者への乗り越え点
さて、(1)身体を通じて世界と新たな形で出会いたいという他者への志向と(2)自分の体や他者の身体を自分の思う通りに服従させたい・そこから快楽を得たいという自己の欲望への内閉とは容易にすり替わってしまいます。無論この二つは厳密に切り離せるわけではなく村田さんの小説でも、谷沢は何度も伊吹君の身体を服従させようという暗い欲望に駆られます。しかし、最後にはそうした暗い欲望を乗り越えて、伊吹君の身体と出会いなおすわけで、この小説の本領は、(2)をどう乗り越えて(1)に至るかという課題を思春期女子に内在的な視点から描き切ろうとしている点にあるのではないかと考えています。
その乗り越えがどのように描かれているか、ここからは複数の解釈がありうるところと考えられます。私の読む限りでは、成長し性徴が発現する途上の自分の身体が持つ歪さに対して持っていた嫌悪感を谷沢が肯定的にとらえなおすことができたことが乗り越えの主因となっています。
谷沢のクラスではいじめが横行し、常に自分の振る舞いが所属するカーストに期待されるものから逸脱していないかを気にしなければいけない状況が生じていました。その中で谷沢は自分の振る舞いに対する自己監視をすることで教室の規範に順応しますが、ひょんなきっかけからあえなくいじめられる側に回ってしまいます。
そして、いじめられる側に回ることで、長らく恐れてきた「気持ち悪い」という言葉やその類の顔貌に対するネガティブな評価付の言葉をかけられることならびにその際の細かな応酬を、谷沢はむしろ、教室の規範に対する抵抗として捉え返していきます。
それを通じて、谷沢にとって「気持ち悪い」という言葉はそれほど恐ろしいものではなくなっていき、「気持ち悪」さの源泉としての自分の身体にも向き合うことができるようになっていきます。
こうした身体を軸とした谷沢の闘争には、谷沢が住む建設途上のニュータウンと谷沢との関係の変化も織り込まれることになります。小さなころから周囲と異なる自分でありたいという自意識を抱えていた谷沢はそうみられる一つの方途として、ニュータウンを嫌う身振りを自覚的にしてきました。
思春期になると成長途上でいびつな身体を抱える自分と成長途上で発展が宙づりとなってしまうニュータウンとがはっきり重ねられ、街への嫌悪と身体への嫌悪はおおむねイコールな関係として読めるようになります。
そして、大嫌いだった自分の体を聖なるものとして捉え返すのにあわせて、その聖性を育んだ街についても「これ以上嫌いな街に会うことってないんだろうな」と記述されます。「嫌い」が安易に「好き」になるのではなく、「嫌い」たくなるような固有の物質性を持ったものとして立ち現れる。巧みな筆運びです。
おわりに
冒頭で述べたとおり、この作品を読んだ時、思春期の性と身体を文学として描くことに成功しているなという印象を私は持ちました。なぜそう思ったのかというと、①それを描くことを通じてしか切り取られえない世界の側面と、そのように見られた世界に独自な論理(スクールカースト、建設途上の街、谷沢の身体の有機的かつシンボリカルな連結)が描かれている②それが読むことで追体験可能な形で読み手に差し出されている、という二つの理由からです。何をどう描くと文学なのかという問いに答えを出すのは難しいのですが、それが言葉を介して描かれる以上、読み手との共同性を構築する方向に作品が向かおうとしているかということは確実に一つの基準となるかと思います。
…そういえば私も自分の身体が変化する中で、自分の身体に嫌悪感を感じたタイミングはありましたが、どう乗り越えたのだったか。この作品を読み終えて顧みると当時考えていた以上に、それは困難な過程であったに違いないと思われて来ます。私の中にもまた谷沢的な存在がいたのではないか、そのように思われて来るということは、この作品が文学として成立している証左なのではないかと思います。
テッド・チャンにおける〈愛への信仰〉の主題―「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」(2010)から

大学一年生の時、シラバスでふと見つけた船曳ゼミに未だに参加しています。その読書会関連で標題に掲げた作品を読んだので、今日はそれについて考えたことを書きます。
※この読書会の関連で読んだ作品について考えたことをまとめた記事として、他に以下のものがあるので、よろしければこれらもご笑覧ください。
テッドチャンとは誰
テッド・チャンとはアメリカ在住のSF作家です。代表作は『あなたの人生の物語』という短篇集で、原書は2002年、訳書は2003年に早川書房から出版されました。
そして17年の時を経て、2019年にチャンの第二の短篇集『息吹』の原書および邦訳(早川書房)が出ました。
テッド・チャン作品を貫く主題
邦訳『息吹』の訳者あとがきで訳者はこの作家について、『ニューヨーカー』にジョイス・キャロル・オーツが寄稿した長文の書評「SFが描く未来はディストピアとはかぎらない」から引きつつ以下のように紹介しています。
『息吹』では、生命倫理、仮想現実、自由意志と決定論、タイムトラベル、ロボットに搭載されたAIなどに関する現代的な問題が、飾らないストレートな文体で語られ、技術的な発想から倫理的な葛藤が生まれる。[中略]『息吹』に収められた短篇群は、答えのない謎かけのようにいつまでも心に残り、読者を焦らし、悩ませ、啓発し、ぞくぞくさせるだろう―と、オーツは書評を結んでいる。*1
私は正直SFというジャンルが得意ではありません。SFでは現代に萌芽がある科学技術が進歩したのちにありえる世界が、作者の科学に関する知見をもとに一定の厳密さで堅固に形作られている印象があるのですが、私はそうした学的厳密さに息苦しさを覚えるタイプで、端的に読んでいて疲れてしまいます。それでも頑張ればフォローすることは出来るのですが、なかなかその気にはなりません。したがって、早川文庫などにはほとんど食指が伸びず、伸びたときでも読み切らずに終わってしまうことがしばしばです。
ところでテッド・チャン『あなたの人生の物語』に関しては何よりもまず短篇であることや、高校時代の友人が強烈に勧めてきてくれたことから、何とか読み切ることができました(しかし今改めて読むと、当時その内容の大部分を理解していなかったことがわかります)。
テッド・チャン作品はジャンル的にはSFであるものの、その重要な主題はと問われた場合熱心な読者の多くが〈自由意志の可能性〉と並べて〈愛〉と答えるのではないでしょうか。科学技術の発展は人間の認識のありようや生のスタイルを変えてしまいますが、その中で都度新たな角度から試される、人間性―人間が人間である限り捨て去ることができないもの―の一つの核心としてチャンの作品では〈愛〉が掲げられているように読めます。もちろん短篇それぞれに〈愛〉の主題の現れには濃淡があるのですが、今回の記事の題に掲げた「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」については、親子愛に近いものが主題です。以下筋を大まかにまとめてみます。作品中でディテールは詰められていますが、到底すべては理解がおよばず、一つ一つについてここで説明しきることも難しいのでその辺りは割り引いてお読みください。
「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」(2010)の概略
物語はデジタル生物である「ディジェント」というAIを一から育てるブリーダー役の女性・アナと、同じようにディジェントを育てるデレクという男性に焦点化した語りで構成されています。ディジェントのブリードには人間や動物と同じくらいの時間がかかることになっており、アナはそれを自分の実の子のように愛します。しかし、ディジェントとそれが稼働するプラットフォームのプログラムは急速なIT技術の進展の中にあって徐々に古びていき、セキュリティ上の問題が生じたり、サイバースペース上でできる活動の範囲が狭くなっていったりするなど、育成したディジェントが一個の人格として人間が通常持つような権利が事実上保証された上で自由にのびのびと生きていけるような環境を整えるだけでも大変な労力がかかるようになってきます。
アナとデレクは、育てたディジェントの今後を考え、彼らのプログラムをアップデートするための資金を調達するとともに、彼らが自力で資金を調達することができるように雇用先を探すことを試みますがどちらも奏功しません。最終的に彼らに資金提供を提案してきたのはディジェントを性的消費の対象として用いようとする会社でした。
もともとディジェントはソフトウェアで、身体を有しておらず、生殖行為をしないので性欲もなければ性的快楽を感じもしません。資金提供を申し出た会社はディジェントのプログラムを書き換えて性的な回路を確保したうえで、人間と同じような感じ方・考え方をするディジェントの経験を操作し、対象顧客との間に幸福な性愛関係を涵養しようとします。彼らの目的は、両思いの人間同士がもつ性愛の体験と同じものを提供することができる娼婦を作ることです。ディジェントの経験を操作できれば、対象顧客に自然な形で惚れ込んだ人間と同じプログラム上の人格が生まれるため、それを利用して所期の目的を達成しようとするわけです。
当然娼婦にするためにディジェントを育ててきたわけでないオーナーたちは反発しますが、自分から進んで快楽へと開かれていこうとするディジェントが現れたこともあり、一部はこの提案を受け入れることになります。
〈愛〉をめぐる物語
この作品のはらみ持つ主題はいくつもありますが、私が面白いなと思ったのは以下の二つの主題の関係です。まず作品中で私が注目する二つの主題がどのように現れていたかを示します。
①愛が犠牲にするものの大きさ
アナは自分のディジェントであるジャックスを気遣い始めてから人生のほとんどの時間をジャックスの教育に費やすことになります。現実世界でアナは結婚しもするのですが、夫との関係はわずかにしか語られません。
手をかける相手が実の子であれば社会的承認は得られ、法制度上も守られますが、対象がソフトウェアなだけに、周囲からアナは折に触れて理解不能なふるまいをする人物として扱われてしまいます。それでもジャックスのことを愛し続け、彼らの擬似的な親を自認するアナの様子から、愛というものが犠牲にするものの大きさが納得されます。
②性愛が構築されたものとしてありうること
作中では子供を性的存在にするかしないか、ブリーダーやディジェント自身の判断に委ねられています。ディジェントを娼婦にしようとする会社が登場したことで彼らがその選択を迫られていることから、ディジェントを性に目覚めさせることが、彼らが性的搾取の構造が組み込まれることとイコールになっていてなかなかに過酷な状況です。しかしこれは案外現実のアナロジーとしてもとらえられます。たとえば自分の子を性的存在としての「女の子」として育てることは彼女を社会で主流の性規範に組み込むことを意味しています。大分レベルは違うことを承知の上でいえば、現実において子が性的搾取の構造に組み込まれて行く際、親が、子を娼婦として売り飛ばす、というようなわかりやすいことをしない場合でも、言説実践のレベルにおいては相応の責任があることになります。
作品中ではディジェントを娼婦として扱おうとする会社の社員が子供のころは男性とキスしたい、付き合いたいとは思わなかったけれど、教育の結果もあり、男性とのお付き合いを楽しむようになった、というようなことを語ります。この社員の語りは性愛が多かれ少なかれある主体に外から植えつけられたものによって駆動されることもある現実に言及することで、ディジェントの経験を操作して、本来彼らが好きにならなかったであろう人を好きにさせるのも注意深くやれば必ずしも彼らの権利の侵害とは言えないことを示唆し、彼らの会社の行おうとしていることを倫理的に正当化する役割を果たしていました。
〈愛〉に固有の価値とは何か?
①だけ見るとやはり科学技術が進展する中にあって〈愛〉というものの価値を改めて強調しようとしているのかなと思われますが、②まで来ると、そうした〈愛〉自体が教育により構築されたものであるということが強調され、翻って①で見られたアナのジャックスに対する外から見ると「狂信的」とされうる〈愛〉が一瞬脱神秘化されるような印象を受けます。しかし、チャンの力点は、そのように〈愛〉が構築されたものであるという前提を引き受けるにしても、その上でなお、ある主体が抱く〈愛〉には固有の価値があるというところなのではないかと考えられます。
チャンの思考実験的世界は様々な側面からある主体がある対象に全く偶然かつ運命的な形で内発的に抱いてしまう感情としての〈愛〉の価値を掘り崩そうとしていますが、だからこそ、ジャックスのために死力を尽くし、ジャックスを娼婦として差し出すことを拒絶してソフトウェアの内面の自由を守ろうとするアナの姿は際立ちます。そして、ジャックスを娼婦として差し出さないアナの振る舞いは、ジャックスが操作されることのない自由な恋愛をしうる可能性を担保することともイコールで、それは自分自身がジャックスに抱くような愛の内発性を擁護しようとする行いともとれます。
〈愛〉固有の価値とは何か。その答えが小説内でわかりやすい形で提示されているようには思われません。しかしそれはこの小説の瑕疵ではなく、むしろ小説を小説足らしめる魅力的な空白となっていると考えられます。というのも読み手としての私は、この流れでどう〈愛〉の価値を主張するのだろう、と問うことによってこそ、小説と最後まで付き合うことができたからです。あえていえば〈愛〉固有の価値があるのかないのかはっきりわからない状況下で、しかしその固有の価値を信じ、守ろうと奮闘を続けるアナの姿こそが、チャンの差し出した回答なのだと考えられます。
〈愛への信仰〉の主題?
以上を前提として言うのなら、私はテッド・チャンの小説の主題として〈愛〉、〈自由意志〉よりも、〈「愛」や「自由意志」と呼ばれているものの持つ価値がありうることへの信仰〉が挙げられるのではないかと考えられます。その存在が自明ではないそれらがありうるということを信仰する人間のありようを描くことを通じて、チャンは科学技術の進展の中で磨耗することのない人間性を描き出そうとしているのではないでしょうか。
近況報告

随分長らく更新が滞りました。ちょくちょく書こうかと思うタイミングはあったけれど、書く気にならなかったのはほかに書くべきものが山ほどあってエネルギーを吸い取られていたから。他のものを書くことで、ブログを書きたいという思いを鎮めることはできないけれど書くことに費やすことのできるエネルギーはやはり有限なので、ブログに書きたいことがあるなあと思いつつできなかった。10月から11月は研究面・仕事面でのピークであまり記憶がありません。
今、次の職場で働き始めるまでのお休み期間中なのですが、平日昼間ふらっとサイクリングしてみて、太陽のもと鮮やかにせりあがる家並や街路樹、小石川植物園の椿や梅の花を見るにつけて、そうした外の世界の諸物との関係の中にある自分というのを忘れ去っていたことにはっきり意識的になりました。会社のパソコンのモニターの中、家のデスクトップの中、本の中、頭の中だけで生きているわけではなく、私の体はこの世界でいろんなものと並んで在るはずなのに、そうしたありようを完全に忘れていました。晴れた日に道を歩くだけで感動してしまう。どれだけ疎外されていたのか。ちょっとリハビリが必要。普通に生活している分には至って普通なのですが、例えばYouTubeでNコン小学生の部を見て、単純な抒情がまっすぐあらわされた曲を子供たちがにこにこしながら(作られた笑顔ですが)歌っているのを見るとあっさり涙が流れていたりする。いくつかの部分については自分で驚いてしまうほど脆くなっています。この半年のダメージといってしまうのは簡単だけれど、そうじゃないのはよくわかっています。もともと弱かった部分がうずいている感じがあり、これは30代が近づいているゆえの何かの変化なのでしょうか。別に悪い気はしません。若干戸惑うだけ。

そういえば10月から11月までの記憶があまりないのは、仕事面・研究面で忙しかったからだけではなく、小説を書いていて頭を持っていかれていたからでもあるのでした。小説を書いたのは小学校高学年の時がはじめて。中学・高校では書かず、大学に入ってから演劇の脚本を書くようになってまた小説を書くほうに少しずつ戻っていきました。
それで、何もこんな時期にとは思うのですが、10月にどうしても書きたいという気持ちになり、学会発表の準備と仕事との合間を縫ってともかく書いていました。それを書き終えるのと学会発表(+学内発表)が終わるのとが同時で、12月のはじめ一旦全部収束してアパシーになり、マックで宙を見つめながら2時間くらい過ごしたりして、早回しのように日々が過ぎ気づいたら年末になっていたのですが、ここでまた小説を書きたい欲が沸き上がってきて10月に書いていたのとはまた違う小説を書き始めてしまいました。小さなころから苛烈な勝負の世界で戦う子供の思春期にかけての内面が描きたく、ちょうど興味のあった囲碁のプロ予備軍について書いてみようと思ってからは朝から晩までひたすら囲碁のことばかり調べ、今年は土日などの都合で正月休みが9連休くらいあったのですが、すべてその調べで消えました。
しかし、自分のほうが勝っているのか負けているのかわかるまでにこれだけ経験が必要なゲームも他にないのではないだろうか。…いや、本当に勝ってるのか負けているのかはどのゲームであっても判断するのは難しいけれど、例えば将棋であれば王将が危なそうか、大丈夫そうかはとりあえずまあなんとなくわかる。しかし囲碁の場合自分の全体的な色がよさそうかは初心者には「とりあえずまあなんとなく」もわからないと思う。
そんな風にして年末に書き始めた小説が一定の分量となり、そろそろあきらめをつけなければならないだろうとなったのが先週末。連絡がとれなかった友人から連絡があり、話をしている最中にふと、終わらせなければならない、と強く思いました。終わらない小説でもいいのだけれど、自分が生み出した想像力の世界にそれなりの強度を持たせたい、そのためにはある程度の完結性が必要とは思い、日月火と本当に朝から晩まで取り組んでいましたが、私の小説の書き方は、大学・大学院のころと現在とでだいぶ変わったなと思いました。
10月に書いていたのも含め、ここ4か月ほどの執筆は「充実しているけれど本当に消耗する」経験。消耗というのは何を示しているのかと言えば、第一に世界の往還に消耗する。書いている世界に没入するのもそこから自分を引っぺがして現実に帰るのも体力が必要。例えば会社に行く前に2時間書いたりすると、出社するころにはかなり疲れていて「もうひと眠りしてから会社行きたいな」などとおよそ社会人としてありえないことを思ってしまったりしました。睡眠時間は基本8時間くらい必要になりました(それまでも7.5時間は必要でしたが)。

第二に、書いたものを読みなおすことで大きく感情が刺激されることに消耗します。これについては、どういうことなのかやや長い説明が必要です。まず一旦ちょっと遡ったところから話を始めると、大学・大学院時代は比較的書く対象との間に距離をとることができていて、〈どう書くか〉に注力するウエイトが高かった。当時の私は小説を書くことを通じていかにそれまでにないような言葉の可能性を開くかということに取り組もうとしていたのでした。そのため、物語内容については、もちろん自分が欲望する内容を書くのですが、読者がどんな物語を読みたいと思うか、ということを考えることも多かったです。つまり、物語内容をある程度客観視できていたのですが、それは自分の欲望と物語の進行との間に距離があるということでもあり、なかなか続くプロットを書くことができませんでした。物語の面白さの基準を外においていたので、自分にとって面白いようにあまり感じられなかった。この時期の私の小説は書く内容が尽きて中絶したものが多く、分量としては基本短篇、多くても原稿用紙100枚くらいでした。
そして、自分の偏った言語使用を分析し、抽出された特徴をさらに複雑に屈折させ濃密にしたような文体なので、今読み返すと、「自分としては悪くない(というか、濃密でよい)と思うけれど読ませられるほうは大変だろうな」と感じられてしまうものに仕上がっています。しかしまあともかく、20代の自分が自分の体をどう言葉の使用に反映させようとしていたかはよくわかり、〈自分研究者〉笑としての自分にとっては史料価値が高いしいつかなんらかの形でリサイクルできるだろうと思われるものに仕上がりはしました。
それに対してここ4か月の執筆では、想像した物語のプロットを書きたくて書きたくてしょうがないということが第一にあり、表現手法としての言語の使用についてあまり意識しなくなりました。すると、読者がどんな物語を求めるかよりも自分がどんな物語を欲望するかということを考えて書いたものが結果物として現れ出るため、書く際にも書いたものを読みなおす際にも自分の欲望が刺激されて刺激されて仕方がないのです。自己同一化することのできる登場人物も以前に比べて増え、一度読み直すだけでも相当感情的なアップダウンを経験することになりました。
嫌な話ですが反省がてら書くと、山場については書きながら涙がにじんでいたし、「これはよくない。全然作品と距離が取れていない。次の日に冷静になって読み直そう!」と思い立って9時間寝て読み直すと今度は、書きながら書いたものを読んでいた前日とは異なり、続く言葉を考える必要がなく純粋に物語自体を受け取ることになったからか、前日とは比べ物にならないほど感情的な昂りがあり、しゃくりあげて泣くような状態になってしまいました笑。自分の書いたものを自分で読んで泣くなんてこれまでになかったので動揺したのを覚えています。
それはそれで気持ちいいというか、カタルシスを感じる体験であったし、自分がどんな物語に感情的に揺り動かされてしまうかを考えるきっかけとなったので自己認識も深まったのですが、一方でやはり書き手として書くものにどう距離をとるのか、今の書き方を続ける限りにおいては再考しなければならないと思いました。少なくとも、人に読ませるのだったら。
そしてまた、こうした書き方は体力的につらいものがあるなとも思いました。細かな表現を推敲するたびに都度心動かされるほど没入すると本当に消耗します。「別にいちいちそんなに入り込まなくていいのではないか」と思われるかもしれませんが、第一に自分の欲望する物語なので勝手に入り込んでしまうし、第二に入り込んでこそ踏み出せるもう一歩というか、その時でこそ書き継げる表現があるので、なかなかそこをスキップするつもりにはなりません。
ということでここ数日の推敲作業と終わりを見つける作業で生活リズムはぐちゃぐちゃ。スイッチ切れる直前まで疲れ、「ほぼ限界だけれどキリのいいところまで、最後に30分だけ推敲して寝よう」と思っても、箇所によっては読み始めると入り込んでしまい、気が付くと明け方3時を回っていたりします。ただ、そういう時も疲れはたまっているので、次の日の活動を始めるのは12時になったりしました。

休みがあったら読みたいと思っていた本はいっぱいあるのですが、それらのうち読むことができたのはごく少数です。「読みたい」というのは欲望ですが、自分が自分の欲望するとおりの物語(読みたい物語)を現に書きついでいるので、読みたいものと言えば何よりもまず、自分が書いているものになってしまいます。したがってともかく起きるとまず自分の執筆中の小説を読んでしまう。自分が持っていかれる、消耗する、へろへろになって「夜は違うことをするぞ」と心に決めながら夕寝をする、起きる。何となく書いていた小説を開いてしまう、自分が持ってかれる、この繰り返し…。
で、そんな執筆にけりをつけたのが今日でした。
大学でシンポジウムを聴き、途中で抜け出して図書館で作業。今日も朝方まで頑張るぞと思いはしたのですが、結局全体の進捗8割くらいで限界を迎えてしまいました。消耗で推敲ではなくただ読むだけになってしまっている。いくつか大きな問題が残っているが、それを解決するよりも読むことで一秒でも長く小説世界にとどまろうとしてしまう。やはり少し距離を取らなければならない。しばらく寝かせなくてはならない…そうは思いながらも自分の小説を読み続けてしまう自分を、パソコンを畳むという物理的な手段をもってクールダウンさせます。いったんあきらめをつけないと寝かせることもできない、と思ったので上で少し出てきた友人に送らせていただきました。持つべきものは信頼できる読み手としての友人。
そういえば私は大学で文芸サークルに入ろうと思ったことが一度あったのですがいくつかのサークルが出している文芸冊子の質が低い【ように見えた】のでやめてしまいました。若干後悔しています。今改めてどっかにしまってある(?)のを引っ張り出して読み直す気にはならないので本当に質が低かったのかそうでないのか定かではないのですが、当時は本物の馬鹿だったので、多分勘違いでした。万が一本当に質が低かったのだとしても、この歳になってわかるのですが、書いた作品を読んでくれる友人を持つことができるというのは掛け値なしに貴重で、書いたものを読みあえる関係性構築の場として、文芸サークルは重要だったなと思います。当時の私は全然思い当たりませんでした。結果物ばかりを見ていた。そもそもサークル的な集まりについての理解が決定的に浅かったのだと思います。(なんであの人たち群れてるんだろう?というようなことばかり考えていた)
閑話休題。作品を読んでくれる友人に送ってこれで手を離れたということになるので、多少は落ち着けるはず…と思っていたら本当に緊張がほぐれたのか3時間も夕寝をしてしまいました。
大変だった…。心なしかやつれたような。気づくと一日一食それも21時ころにやっと食べた、ということになってしまった日もあり、これまで結構どんなときでもお昼と夜は規則正しく、それも他の人に比べて多めに食べていたのですが、そこすら不安定な生活になってしまいました。こうした根を詰めた創作活動は休みがなければできないので、本当にできてよかったけれど、課題は山積している。これでいい小説が書けていたら言うことないのだが、そんなことには到底ならないのが難しいところ。ま、大抵の物事は二か月とかでなんとかならないので、これだけ二か月で済ませられると考えるのはおかしな話でしょう。

根詰めて小説を書いた一番の成果は、「ともかくこれなら過剰なまでにできる」とわかったこと。社会人になって思うのですが、優れた仕事というのは何らかの過剰さをはらんでいます(誰もが優れた仕事をする必要は全くありません!念のため)。そうした過剰さと同じものを訓練を通じて発揮することは十分可能だと思いますが、それにはなかなか労力がかかる上、継続できないと長期的には質は下がる一方。それではどのような仕事なら過剰さを発揮しつつ継続できるか。それは個人の性向や個人史に根差しているため、自分で見出すしかないと思います。とはいえ、それはいつも呼吸をするように続けていることや抑え込んでも抑え込んでも断続的に沸き上がる欲望の中にあるので、冷静に自分の日常を振り返れば見出せるはずではあるのですが。私の場合こういう風に書くことを一時的にならできるとわかりました、が、これだけ消耗することを継続できるのか。そしてもし継続できるのなら、それは対価をもらえる仕事になるのか(そうでなくてもそれはそれで続けますが)、見極めなければならないと思います。
***
せめて外の世界を若干也とうかがう機会くらいは多少持とうと思い、この数日、執筆場所はいろいろ変えていました。主には家から自転車で行ける文京区の様々な喫茶店。そこに向かうまでの家並は前述のとおりよかった。特に小石川。一目見ただけでお金も手間もかかっているとよくわかるような、デザイン的に優れており清潔で品のあるお家がぎっしりと並ぶ閑静な住宅街。そこを歩くとこちらも居住まいを正そうという気になります。駒場の西側と同じものを感じた。
小石川は基本言うことなしなのですが唯一、地下鉄の駅までは遠いかな…茗荷谷、千石、春日、どこにいくにも徒歩だと15分くらいはかかりそう。ちなみに同じ文京区でいえば目白台とかも不便そう。
文京区は公共施設にもお金をかけており、歴史と教育を大事にしていて、都心の割にはがやがやとうるさい場所が少なく、道も広め。一生ここを出たくない。ゆくゆくは小石川とかにお家を構えたいなと思いつつ、勤め人なのでしばらくは駅近の下町エリアに住みます。
***
最後にお仕事について。転職します。その事情については多分そのうち書きますが、ここでは一旦以前働き始める際に書いたエントリを貼り付けておきます。うーん新しい生活への〈不安と期待がないまぜになった感覚〉笑がある。総括すると、20代半ばまでずっと学校的なものの中にいた私にとって就労はもっともっと異世界体験のようなことに満ちているのかと思っていたら、案外普通でした(周囲の人も「働き始めた割には案外変わらないなこの子」と思っていたはず)。
本当に恵まれた職場だったので大きな不満はなかったのですが、人が社会で働くこと一般についてはちょこちょこ考えることがありました。
この三年間で一番大きかったのは一人暮らしを始めたこと。仕事とは直接関係ありませんが、私の人生にとっては革命的な変化でした。一人暮らしを始められたことの一点をもって、働きはじめたのは成功だったと自信をもって言えます。私生活については、間違いなく人生最良の日々=今
以上乱筆失礼しました。
作家・古谷田奈月さんについて 三島賞受賞作・「無限の玄」(2017年)まで

最近話題作を繰り出している作家として私は古谷田奈月さんに注目している。二度くらいにわけて、ちまちま調べた情報や、読んだ古谷田小説の感想について書きたい。
なお、他に村田沙耶香さんや高山羽根子さん、高橋弘希さんについても関心があり、それについては以下の記事に書いたので、よろしければ合わせてご覧いただけると幸いである。
1、古谷田奈月とは誰か。
古谷田奈月は、現在純文学系の文芸誌を中心的な活動の場とする新進作家である。古谷田の小説の多くに共通するのは、家父長制社会下における男女の生に独自の観点から問題意識を投げかけつつも、そうした社会に生きる若者たちの個人史によりそい、彼らを肯定的に描き出す語りのありようと言えよう。
古谷田は、1981年に千葉県我孫子市に生を受けた。二松学舎大学文学部国文学科を卒業してのちは、しばらく派遣社員などをして働いていたようだが、その後本格的に執筆に取り組み始める。
2013年には、「今年の贈り物」という作品で第25回日本ファンタジーノベル大賞を受賞した。同作は、その後『星の民のクリスマス』(新潮社、2013年)と改題されて出版される。これが古谷田のデビュー作となった。2016年には光文社から『リリース』という作品を出版している。この作品は2017年に第30回三島由紀夫賞候補となったが、当選はしなかった。しかし同作は第34回織田作之助賞を受賞している。
2018年には、「無限の玄」(『早稲田文学』増刊女性号(通巻第1026号)、2017年)で第31回三島由紀夫賞受賞し、「風下の朱」(『早稲田文学』2018年初夏号(通巻第1028号))で第159回芥川龍之介賞候補となった(受賞作は高橋弘希「送り火」)。この二つの作品は一冊にまとめられ『無限の玄/風下の朱』として2018年に筑摩書房から出版され、第40回野間文芸新人賞の候補ともなる(受賞作は金子薫「双子は驢馬に跨がって」、乗代雄介「本物の読書家」)。
2019年4月には長篇「神前酔狂宴」(『文藝』2019年夏季号、のち河出書房新社より2019年7月に単行本化)を発表した。同作では、明治時代の軍神を祀った神社の管理下にある会館で、結婚式の運営にあたる派遣社員に焦点化して語りが行われる。同作は日本的婚姻制度の問題、天皇制と生身の身体を持つ天皇の個人としてのありようとの間の葛藤、新自由主義下の若者における貧困の問題などが描き出される意欲作であり、高い評価を受けている。
以上述べてきたように、古谷田はデビュー以降概ね継続的に作品を世に送り出し続け、その多くが主要な文学賞を射止めたりその候補となるなど、現代文学を孵卵し、世に送り出す文芸誌を中心とした制度——以下では仮に現代文学の「文壇」と呼んでおく——の中で、八面六臂の活躍を見せている作家である。
2、「無限の玄」「風下の朱」執筆まで
前項で述べたように、古谷田のデビュー作はファンタジーノベルである。もともと古谷田は純文学の新人賞に応募していたが、「純文学縛り」が窮屈となり、ファンタジーに向かうことになった。
インターネット上で公開されている下記のインタビュー記事において、古谷田はスクエア・エニックス社(現社名)製の大ヒットゲーム『ドラゴンクエスト』の攻略本から、同ゲーム中に現れる装備など細かなディテールにまで作品世界設定に即した物語が付されていることを知って感嘆したエピソード を述べており、古谷田が想像上の世界を精緻に組み上げていくことへの志向性を有する作家であることがわかる。
しかし、受賞後、今度はファンタジーのようなエンタメ系の領野ではオチをつけなければならないことに窮屈さを感じ、逆に何でも書いて良い純文学が自由に思われるようになったという。
転機となった『リリース』(2016年)
そうして書かれた作品『リリース』は同作品単行本版の「解説」を執筆した栗原裕一郎のまとめを引用すれば、「男女同権やLGBTの権利の確立という理想が実現した暁にはどんな未来がやってくるかを追究した、思考実験的なディストピア小説[1]である。
空想上の社会を描くという点ではファンタジー的想像力に親和的であるものの、テーマは現代におけるLGBT運動と直結しており、社会的な問題に取り組む作家の姿勢が色濃く伺える。古谷田は同作品執筆の経緯について、仲俣暁生からのインタビューにおいて、可能であれば社会的な問題をメインに据えたものを書きたくなかったが、自分の書いていた小説に男性ばかりでてくることに思い当たり、「どうもほっておくと自分は女性を出さないなということに気づき、特に思想があるわけでもないのにジェンダーの偏った小説を書くことに罪悪感が出てきた」 [2]ことが執筆のきっかけとなったと述べている [3]。
そして、同インタビュー中で仲俣が、『リリース』の出版により「社会的な問題意識のある作家、それも技巧的な引き出しが多そうな作家として古谷田さんは認知された」 [4]と述べているように、『リリース』の発表は、古谷田の作家のキャリアにとって一つの転機となったと考えられる。
それは、同作発表後、古谷田が早速、川上未映子が責任編集となった『早稲田文学』増刊女性号(2017年9月)という「社会的な問題意識」に満ちた雑誌に対する執筆依頼を受けたことからも裏付けられる。
「無限の玄」(2017年)の執筆
そして、この執筆依頼は古谷田にとって、初の純文学系文芸誌からの依頼だった[5]。
「無限の玄」は男ばかりの血族で構成されるストリングバンドで絶対的な権威を持っていた父の繰り返される死と再生と、それに翻弄され、揺動しながらも少しずつ新たな形に変わっていくバンドの男たちの共同体を描く。現代社会におけるジェンダー不平等の問題に対する告発を主目的に据えた、「女性」を冠する「女性号」において、「無限の玄」は、男性のみの共同体を描いているという点で他の作品と比して異質なものとなった。
この作品は2018年に三島由紀夫賞を受賞するが、その受賞インタビューにおいて古谷田は「女性の書き手のみで構成される雑誌だからこそ、男性について語られねばならない、しかもそれは、男女が対比的に登場する物語ではなく、純粋に男性のだけの視点で描かれるべきだと感じました」 [6]と意図を述べる。
その上で、自己のジェンダーバイアスについて、「私はもともとジェンダーバイアスの感覚がおかしくて、かなり意識しないと女性の登場人物を出せない」「男性キャラに女性キャラを関わらせると、そこに意味を持たせなければいけないのではないか、つまり「性」に触れなければいけないのではないかという気がした」「私の性自認は女性ですが、作家としての私にとって女性はずっと「異性」でした」と続ける。そして、「フェミニズムが元気になってきて、正直とても引け目を感じました。女性の活躍を書けない作家なんてと恥ずかしくなった」 [7]とすら付け加える。
あえて男性同士の共同体を描いた作品の受賞インタビューで吐露される、やや過剰にも思われるような女性ジェンダーを描くことへの義務感と、それができていないことへの「引け目」の感覚は、古谷田をして姉妹作「風下の朱」の執筆に向かわしめることになる。
3、三島賞記念スピーチについて
続きは次回に回すが蛇足を一つ。
最近話題となった文壇論として多くの人が想起するのは、福嶋亮大の「文壇の末期的状況を批判する」という記事だろう。同記事は『REAL KYOTO』というウェブメディアに2018年8月18日に掲載された。
この記事は、早稲田大学の渡部直己教授によるセクハラ疑惑(一応「疑惑」と書いておく)問題から筆を起こし、盗用疑惑(同上)で一時期話題になり、かつその後芥川賞候補作となった北条裕子の『美しい顔』(2018年)について建設的な批判を展開しつつ、現代の文壇がないがしろにしていると思われる表象の問題を改めて提起する。舌鋒の鋭さと批判性から記事の掲載直後より文学に関係する学者・批評家を中心に広く拡散され、侃々諤々の議論を呼んだ。
福嶋の記事は以下の引用部に現れるとおり、文学に関わる研究者・作家は表象の暴力性に十分自覚的であるべきだ、という主張を中心としている。
いずれにせよ、改めて繰り返せば、文学者ともあろうものがホイホイMe Tooなどと言って、他者の人生に「私」を重ねていくのは、たとえそれがどれだけ政治的に正しかろうと、文学者としては間違っている。Me TooだろうがWe Tooだろうが、気軽に使ってよい言葉では断じてない。たとえ支援の意志があったとしても、他者の人生の苦難に対して「私(たち)も同じ」と乗りかかるのは基本的に傲慢なことである。文学は本来、そのような共感の危うさを――つまり一見して優しげな善意のもつ罠を――教えるためのものである。
ところでこの文脈に乗る形で古谷田奈月に関して言及があったことが、この記事を執筆していた私の関心を引いた。以下の部分である。
もとより、騒動後も渡部と数度メールをやりとりした私は、一連の報道をすべて鵜呑みにするつもりはない(ちなみにインターネットで「疑惑」が報道された直後に、某文学賞の授賞式でさっそくMe Tooをかざして報道に便乗した作家がいるとも伝え聞く――これが事実だとしたら一般論として軽率であるばかりか、後述するように文学者の振る舞いとしても大きな問題だろう)。
これだけでは古谷田に関する言及とはわからないが、三島賞の授賞式が渡部に関する報道の直後である2018年6月22日であったこと、また、朝日新聞のオンラインメディア『好書好日』の記事(「# Me Too」「ハイデガー」「ネコトーク」 三島賞など3賞贈呈式、3者3様のスピーチ(『好書好日』、https://book.asahi.com/article/11637726、2018年6月26日配信)から、授賞式で古谷田が『早稲田文学』女性号についての考えを述べていることを考え合わせれば、福嶋が上引用部で言及しようとしているのが明らかに古谷田であることがわかる。
古谷田がMe Too運動に現れるような他者を安易に表象した気になるPCの陥穽を自覚した上で、あえてニュース発覚直後の、事件を客観視するにたる情報が入ってきていない段階で発言をしたのならよいが、以下のリンク先から見ることのできるスピーチの動画からは使命感に駆られてともかく言及してしまった、という感じが溢れ出ており、問題意識は十分によくわかるが公平に見て拙速な感じはあったと思う。
しかし、こうした前のめりは、作家として書くという本来的に私的な試みを、〈この世界に生きる様々な人々に対してフェアな態度を取らなくてはならない〉という責任意識を負いつつ行う古谷田の誠実さゆえのものであろう。それ自体は好ましいものであるしその誠実さの強度は最近の若手作家にないものだと感じる。違和感を言葉にしようと試み、かつその中で受けた上のような批判を十分に生かし、それに対して(賛成反対問わず)作品執筆を通じて応答していくことのできる潜勢力のある作家であることは間違いない。
それではスピーチからすでに一年半経過し、このほど執筆された話題作『神前酔狂宴』にそれが現れているか。続く記事で言及したい。
===
[1]栗原裕一郎「解説」、所収:古谷田奈月『リリース』、光文社文庫、2018年。
[2]古谷田奈月、仲俣暁生「小説におけるフェアネスと勇気」『ちくま』第572号、2018年。
[3]同上。
[4]同上。
[5]同誌には岩川ありさによる『リリース』論(「クィアな自伝——映画「ムーンライト」と古谷田奈月『リリース』をつないで」、436-444頁)が載っており、古谷田が『リリース』により岩川のような現代社会におけるジェンダー問題を論じる批評を多数発表する論者に注目されたことがわかる。
[6]「受賞記念インタビュー 死が繰り返される世界へ」『新潮』2018年7月号。
[7]同上。
Young HongKongers, please be prepared for a long time fight
This is an English (summary) version of the article below.

How can you get to a point of compromise?
The 2014 umbrella movement for universal suffrage became a major topic of conversation in Japan, but less attention has been paid as to whether it was a success in the end or not. It may be a matter of course, but there is no reason for the CCP to allow universal suffrage. It is true that the movement gained widespread international support with the participation of many citizens, but towards the end the demonstrators were in exhaustion. They were constantly tear-gassed and gradually eliminated. Although the period of occupation was certainly long, it did not lead to negotiations between the government and the demonstrators or to the resolution of the issue through intervention by Western countries.
Demonstration this time has one point in common with Umbrella: How to get to a point of compromise is not clear. If the Legislative Council is effectively a puppet of the CCP, who will be the negotiating partner? How do you identify and negotiate with them? Even with the support of the international community, few countries will intervene in now big and internationally influential China's domestic problems in an effective manner.
Young HongKongers and violence
The students are ready to use violence and prepared to die for freedom.
Here is Hong Kong. Students who joined the protest will prepare their last will.
— Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) September 1, 2019
ON Vice News: Police Draw Guns For the First Time at Hong Kong Protestshttps://t.co/a5LT7a5P7F pic.twitter.com/XJT15yRHWN
I can never agree to this kind of commitment. Violence gives the regime an excuse to arrest them and to use more violence against them. If you take a big risk like violence, you should do it after you see a chance to win.
Watching video above and reading tweet below, I'm afraid I can see a kind of heroic narcissism. It is really dangerous. If you really get some aftereffects at the compensation of violence -for example, physical disability-, would it all right for you? You can't even fight next time.
We create our history. pic.twitter.com/aNkfDPqNMi
— Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) September 7, 2019
please be prepared for a long time fight
These things aren't going to work out tomorrow or near future. Demonstration's going to be an uproar, but when you wake up, you'll notice that things has not changed as you expected. It takes very long time.
Of course, the demonstrators know that. You may think that it is not something that people from other countries say again. I'm sure I have to mind my business (you know Japan is now in crisis too, due to the rise of right-wing forces and historical revisionist).
However, when I see young people in HK who are committed to violence, I want them to be aware of what I wrote again. There will undoubtedly be a great battle, for example, in 2047, when one country two systems will no longer be self-evident. How do you fight if you're burned out or seriously physically injured in this battle?
Whether you graduate from college, get a job, have a baby, or even enter a nursing home, there's probably a pile of problems and you have to keep fighting it. This is only starting point, you definitely know.
I am not pathetic. This is what the democracy is. Through fight for freedom you can make invaluable relationship between fellows.
I would like you to gain the energy to remain persistently involved in this problem from this movement to cultivate the intellectual strength necessary for building a relationship with a CCP and depicting a new social system that will work efficiently in accordance with HongKongers own will. I don't want anyone to have their head broken by the police.
By the way...
When I told my acquaintance who was born in and grew up in HK about 3 years ago that I was supporting civic movements in Hong Kong, she said scornfully, "Joshua Wong is doing it for money." but I would rather respect him if he could do this much just for money lol







