ポスト・ポストモダンの国語教育論について考えたこと 田中実の〈第三項〉理論と公共性
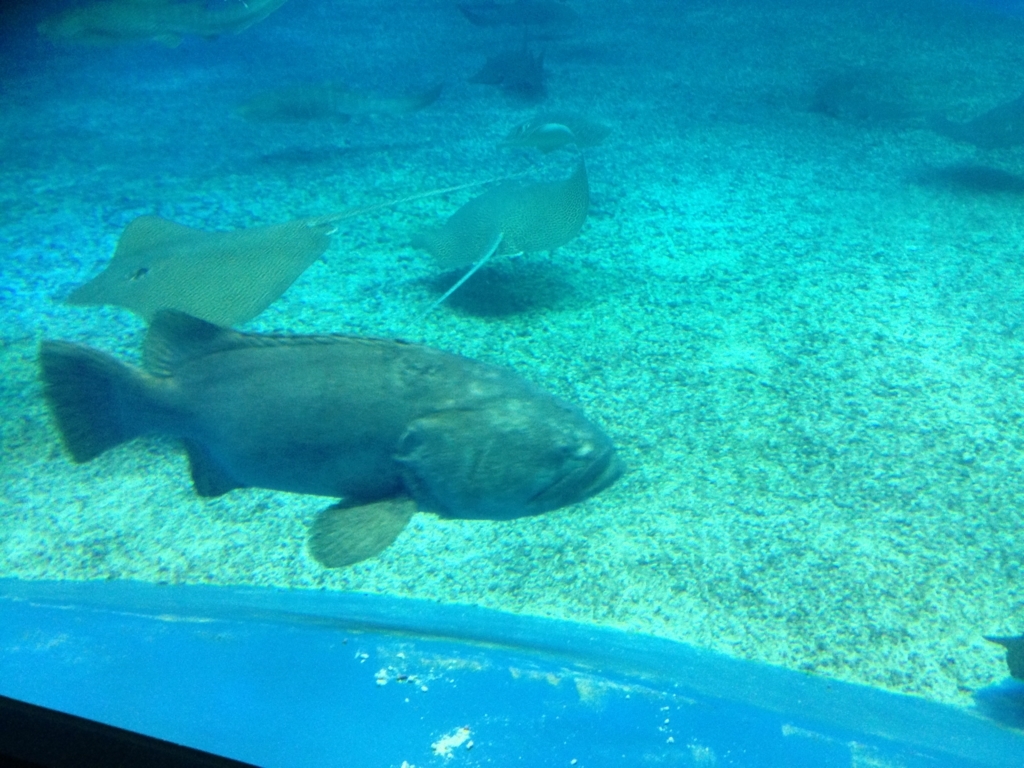
この春から学校教育に関わる現場で働き始めた。毎日がめまぐるしく過ぎていく中で、なかなか考える時間がとれない。
働き始める前に考えていたこと、そして、働き始めて以降に考えるようになったことを一旦冷静に整理したい−−−そのような思いから、数日前より過去に自分が書いた日記や、授業の終わりに提出したレポートなどのうち、教育に関わるものをざっと読み直した。その中で出てきたのが以下の文である。
数年前に授業のレポートとして書いたもので、やや硬い書き方となっているが、今自分の持っている問題意識、つまり今、国語教育はどうあるべきか、という問題意識に通じうる論点が出てきているため共有したいと思う。
以下レポートの本文。
はじめに—田中実の〈第三項〉論について
〈第三項〉論とは何か
「バルトが見過ごしたところ、〈原文〉に《神》は隠れている」[1]と述べ、ロラン・バルトの理論を、その陥没を指摘する形で発展的に継承し、網膜に映った知覚以前、言語以前の〈原物〉としての原文(=〈第三項〉)の影(=〈プレ本文〉)が「どのように読者主体と葛藤し〈本文〉を生成しているか、その現象」[2]を問うことを基本に据えた田中実の読みの理論は、例えば教室における文学教材の読解の際には〈語り手〉に注目する読みとして実践される。田中はこのような実践の目的を「亜流ポストモダン」でなしに「真の相対主義=真正ポストモダン」を克服する手立てとして想定している[3]。
「ポストモダンの克服」としての「価値の基準」の創出
それでは、田中のいう「ポストモダンの克服」とは具体的にどのようなことか。それは、最終的に文学作品の評価を措定することと言ってよい。ポストモダンの克服を目的とした〈語り〉の方法論の実践に取り組んだとする『文学が教育にできること—読むことの秘鑰』[4]という著作の末尾において、田中は「(4)評価へ」と題する項目を設け、伝統的「物語」文学と〈近代小説〉との峻別を意図し、生成論において生成過程の文がそれぞれ等価ではないと判断される事情に触れながら、以下のように述べる。
わたくしの支持する生成論は〈本文〉を探り、決定せんとする価値論を要するものであってアナーキーなポストモダンに留まるのでなく、それらにベクトル、〈作品の意志〉を読み込むのです。定稿を書き上げた芥川には単行本初出との決定的な相違がよくわかっていました。『羅生門』定稿は伝統的「物語」をメタレベルで批評することに成功し、文学に価値の基準を創出したのです。[5]
田中の論を追う限り、ここでの「価値の基準」とは、〈機能としての語り手〉がそこに本当の意味でたどり着くことの出来ない客体(=〈了解不可能な他者〉)をいわば〈わたしの中の他者〉として捉えざるを得ないことへの語り手自身による批評性が顕在化しているかどうかということによって推し量られるものなのだろう。そしてそれは具体的には出来事中心の読みでなしに、小説中において出来事や登場人物が語り手によりどのように語られているかということに注目される中で行われる。これを通して読む主体の「〈自己倒壊〉」と「感銘」が引き起こされる[6]とされている。
相対主義は本当に超克されている?
ところで、上の田中の引用には多くの問題があることもまた容易に指摘される。例えば、「芥川」という作者が実体化し、作者「芥川」が何をわかっていたか、田中が代弁することになっている。
また、田中の言う「生成論」は、テクスト生成を省みるに当たって最終稿を優位と置き、〈作品の意志〉という謎の進歩的な「ベクトル」を採用してしまう点で、文学研究の場で一般に受け入れられている生成論とは異なっている。生成論はむしろ最終稿以前のテクストを見る中で、カノンとして存在する最終稿の権威を相対化する視点を供給するものであるはずである。
語り手に着目する方法論は確かに有益だが、教材の「価値」という概念が、田中にとってそこに原文の影が読み取りやすいという基準によって実体化されてしまうならば、これもまた一つの、いわばポスト・ポストモダンの文脈における正解到達主義と言えるだろう。田中の論文の題名、たとえば「奇跡の名作、魯迅『故郷』の力」[7]を読む際に執筆者にとって危惧されるのはこの点である。「奇跡」や「名作」といった言葉が無批判に用いられているが、「名作」かどうかを不断に問うことこそが教室において〈語り〉を開くきっかけなのではなかったか。田中は生徒にとってだけでなく自分自身にとっての〈自己倒壊〉の契機を真摯に取り込もうとしているのだろうか。
これは無論田中だけの問題ではなく、教育現場に広くありうる問題である。ポストモダンの相対主義の克服が相対主義の問題設定をないがしろにするものであってはならない[8]ことは自明であり、「読むこと」を「倫理の問題化」と同定する[9]田中や田中の問題設定を共有するものらが一元的な価値基準の設定に不可避に孕まれる暴力性を看過してはならないこともまた同様にあまりにも明らかである[10]。
現場での実践へ
田中理論[11]は確かに、80年代問題と名指される十人十色の文学教育に代表的な微温的価値相対主義に対するのには有益だったかもしれない。しかし、上記のような田中理論の枠内での「評価」の明文化が行われ始めた今日においてその理論をとりわけ現場での実践から批判的に再検討することは有意義と思われる。
田中理論を背景としながら、その実践を行う齋藤知也の著作『教室でひらかれる〈語り〉:文学教育の根拠を求めて』[12]と参照しながら、田中の提唱する教材の「価値」「評価」が教室での実践においてどのように扱われているのかということに関して、以下では簡単に検討する。齋藤は田中理論に影響を受け、それを後ろ盾にして授業を行っているが、田中理論を読んだ執筆者からすると、その実践は理論の問題を指摘するような批評性を持っていると思われる。
国語科教育と民主主義
齋藤の『教室でひらかれる〈語り:文学教育の根拠を求めて』という著作は国語科における教育が民主主義における主体を構築するのにどのように貢献しうるかという観点に取り組んでおり、そこで田中理論は読みにおける〈自己倒壊〉を促すことにより、個々人の価値観を揺り動かし、自分だけの見方(〈わたしの中の他者〉)を超えて共有されるべき価値の存在へと視野を広げる、その一助として考えられていることがわかる。
齋藤の述べる「価値」とは
それでは、冒頭で問題化した「価値」という言葉はここではどのように使用されているか。「価値」という言葉が前景化するのはIIの第三章と言って良いだろう。齋藤は内田樹の『下流志向』を引きながら、「消費主体としての自己確立」を強いられた子供たちを「民主主義の主体」としていくために、必要とされるものとして「価値」を問う読みを挙げる。
〈わたしのなかの他者〉〈わたしのなかの文脈〉を倒壊しようとし続けていくことはすなわち、「自己を問う」ことであり、〈価値〉を模索していくことである。その時、一見しただけでは「カンケイない」と思っていた世界に対する自己の「ものの見方」が問われ、切実なものとして見えてくる。(中略)〈価値〉を模索し合い発見していくことは、個から出発して、〈公共性〉を模索していくことでもある。[13]
上を見る限り「〈価値〉を模索」することは「自己を問う」ことと同義であると言える。つまり、「価値」とは「自己」、もしくは自己を構成する価値観に近いものと捉えられていると言えるだろう。この氏の定義を用いて冒頭の田中の引用を読み直せば、「〈本文〉を探り、決定せんとする価値論を要するもの」という部分は決定的に奇妙なものに思えてくる。
というのも、齋藤の用語法の通り、〈価値〉(=自己=主体)は決定不可能であるからであり、それは何らかの基準になり得もしないからだ。〈本文〉も〈価値〉も決定したと思われる時にこそむしろ最もそれを「模索」し続けることが求められるものとしてあるからである。そしてそれこそが〈公共性〉の模索であるということに執筆者は賛同する。それでは、公共性はどのように捉えられているか。
「公共性」は自己倒壊なしでは到達できない?
齋藤が行った第59回日本文学協会国語教育部会夏季研究集会の基調報告は「文学教育の転回と希望:ことばの〈公共性〉をめぐって」という題に現れる通り、「ことばの〈公共性〉」をテーマにしたものと考えてよいだろう。しかし、ここでは「ことばの公共性」を問うことは「主体の〈倫理〉を問題にすること」でもあるとされる[14]以上に議論は深まっておらず、外在的な「倫理の価値基準」の必要性を示唆する方向に論考が収斂してしまう。
執筆者は、個人の内面に存する〈倫理〉の問い直しを通して〈公共性〉に至ろうとするこのような議論が、内面の自由・良心の自由と両立するのか確信が持てない。理論はその提唱者や、その活用者の顔の見えないところで生き延びていくものであるため、とりわけ教育という教師の恣意性を排除できない現場に関わる議論に関しては細心の注意を払ってなされるべきものと考える。よって、このような論の流れには賛同できない。
しかし、対案として〈公共性〉を〈他者の声を聞くこと〉の倫理性を前景化しながら説明することはありうるし、また、これは田中理論や齋藤の実践と大きく矛盾しないと考える。以下それについて簡単に述べる。
教室で公共性を模索すること
テクストの他者性に耳をすませる行為
〈語り〉の方法論は、教材として教科書に載るような著作における語りもまた、教室で生徒達が語るように語ることの延長にあり、自己の認識の枠内から容易に外に出るものではないことを生徒らに気づいてもらうことが出発点と言えるだろう。そのようにテクストを一旦自分たちと同じところに下ろしてこそ、テクストの中で現れる自己への批評性がそこにおいて賭け金になるのである。
どのような語りも相対性を免れないことへの気づきを通して(還元不可能な複数性をくぐり抜けて)教材価値を相対化し、その上で再びそれを教室の中で築き上げる試みが齋藤の実践であり、この実践は他者性を不可避に孕むテクストに響く語り手の声もまた、漂白された声でなく、誰かがどこかで必要に駆られて発したものであることを意識して、その声調を聞こうとする試みであると言える。
耳をすませることの倫理性から公共性を導けないか
ここにおいて「倫理性」は上で述べたように、ともに教室にある他者(=他の生徒)の声、そしてその他者の一人として教室に参画するテクストの声を聞くことに求められることになるだろう。
それでは、なぜ他者の声を聞かなければならないのか。それは、自己というものが他者との関わりにおいて存在するものだからである。国語科教育における〈公共性〉はこの時、教室でともに読む参加者が「私」と無関係でないことを引き受けて、自己の読みを展開し、「価値」を模索することに求められる。
「価値の模索」とはこの時、「自己を問う」ことであるが、それは「教室の読みを問う」ことと接続するものであるべきであり、両者をどれだけつなげることができるかが公共性が担保されているかどうかの指標となることだろう。そこでは個々人の〈自己倒壊〉でなしに、個々人=教室の読みの変容と構築が求められる。このように他者との分有の可能性に開くことに強調をおいてこそ、民主主義の教育の中における国語科教育の位置も鮮明になるのではないかと思われるのである。
結論——〈第三項〉と公共性
文学作品を読むことが公共性につながるとしたら、それは、なによりもまず、私たちが文学作品をどう聞き取るかという実践の方法的態度を身につけるという位相においてである。そう考える時、「十人十色の文学教育」に見られる「微温的相対主義」が見落としたのは「原文」や「了解不可能な他者」というよりは、よりオーソドックスに、「公共性とは何か」「個々人が好き勝手に意見を述べ合うことが民主主義であるのか」という問いであったのではないか。
============
[1] 田中実・須貝千里編『文学の力×教材の力 理論編』(教育出版、初版2001年)、24頁。
[2] 同上、36頁。
[3] 田中実「奇跡の名作、魯迅『故郷』の力:大森哲学との出会い、多層的意識構造のなかの〈語り手〉」(『日本文学』62巻第2号)、40頁。なお、このポストモダン観は曖昧であると同時に、多くの問題がある。例えば田中は主客の脱構築をポストモダンの相対主義(アナーキズムとルビがふってある)を超えようとするもの(そしてできない虚妄)として設定しているが、脱構築は主客の境目に関わるものではないし、相対主義を乗り越えようとするものでもない。
[4] 田中実・須貝千里編『文学が教育にできること:「読むこと」の秘鑰』(教育出版、2012年)
[5] 同上、340頁。
[6] 田中実「〈主体〉の構築」(『日本文学』62巻第8号、2-12頁)を参照した。
[7] 書誌情報は脚註3を参照。
[8] 相対主義の乗り越えとは、相対主義がすでに乗り越えた一元的な価値基準を再導入するということによっては果たされない。ある価値基準を設定することの不可能性を十分に自覚しながら、それをあえて主体的に選び取ることでしか、価値基準の設定はありえないことを自覚し、不断に自己の価値の脱構築を図る身振りを伴わなければ価値基準の仮構の倫理性は担保されない。このように倫理性とは理論に内在するのではなく、パフォーマティヴな振る舞いの中から顕現するものであり、この倫理性が担保されないと、ある価値基準は容易に相対化されうることになる。相対主義の克服は理論を構築した瞬間に済む一回的な出来事でない。つまり、理論はそれ自体常に「評価」にさらされ、それを取り込む可塑性を示す必要がある。
[9] 田中・須貝編前掲(→脚註1)、335頁。
[10] 以下では詳細に触れることができないが、そのような暴力性に何よりも向き合ったのがテクスト論の後継者である脱構築批評であり、田中がその価値をあまりに軽く看過していることがおそらく石原千秋や加藤典洋の反感を呼んでいる。
[11] 須貝千里は石原千秋との討論(『日本文学』64巻第4号、40頁下段)において田中の〈第三項〉に関する議論を「田中理論」もしくは「〈第三項〉論」と呼ぶことを提起している。
[12] 齋藤知也『教室で開かれる〈語り〉:文学教育の根拠を求めて』(教育出版、2009年)。
[13] 同上、176-177頁。
[14] 齋藤知也「第59回日本文学協会国語教育部会夏季研究集会基調報告 文学教育の転回と希望:ことばの公共性をめぐって」(『日本文学』56巻第12号)75頁。
とただ貼り付けてしまったのだが、昔書いた以上のレポートを読み直した時、改めて感じられることに関しては、また次に書くことにする。
===
こちらもどうぞ


