「安心してどうするんですか死ぬだけなのに?」 うーん
久々の更新であるのに、前回の更新から経た歳月などなかったかのように書いてしまうのだけど、飯田橋文学会主催の文学インタビューを聴いて来た。今回は詩人の高橋睦郎さんに対するインタビューである。この企画は現代を生きる作家の生の声を聴くという趣旨で、インタビュー内容は後日noteなどで公開(有料)されたり、東大出版会から出版されるのだが、その元となるインタビューの収録を講演会のようにして一般公開しており、それに行って来たのである。企画について、詳しくは以下のリンクから。
現代作家アーカイブは、不可抗力で参加できない場合(実施場所が京都、とか)を除き、これまでほぼ全部参加しているかもしれない。出不精の私としては珍しいことだなと思う。企画を中心的に主導する大学の先生に薦められて出始め、これで都合三年以上になるだろうか。
上記のリンクを参照してもらえばわかるのだけど、インタビューは基本的に対象の作家さんの生き方であるとか、創作の秘訣、文学をどのように捉えているか、などジェネラルな問いをめぐっており、インタビュアーは作家さんがお話しするための材料をちょこちょこ提供したり、進行を司ると行った形。特定の作品や作家の人生の中の特定の時期、その思想などについて狭くフォーカスするわけではないので、正直話が深まることは稀な感じ。しばしばなされる「ーさんにとって文学とはなんですか」「この作品はどういう背景で書かれたものですか」的な問いに関しては、作家がおそらくこれまでも人生の各所で受けて来た問いであり、「その質問の答え、昔受けたどこかのインタビューに載ってるのでは・・・?」とか思わなくもないのだが、語る時の息遣いや、聴衆を前にした時の構え方など、作家の生身の身体性が伺えるのは魅力。それを目的にして行く企画であろう。
高橋さんに関して私は全く知るところがなかったが、以前三島由紀夫に関するシンポジウムでお話しされているのを見て、「話が面白い人だ」と感じていたので、今回参加した。その作品についてはほとんど読んだことがないが、インタビューの中で垣間見えた高橋さんの人生観が面白かった。
どんな話かというと性に関する話で、具体的には結婚のことなのですが脳内で再現したものを無批判に書き出すと
結婚っていう制度は面倒。本当に面倒で、なければいいのにと思うけど、ないとどれだけ自由かといつも思うけれど、ないとみんな不安になるんだよね多分。でも、不安だからなんだっていうの?安心しても仕方ないでしょう死ぬだけなんだから
というような感じ。なかなかグッと来た。今、私は大変安定した生活をしてしまっていて、だからグッと来たのだと思う。
教員の仕事は、うちの学校がゆるいからかもしれないが成果は求められないし仕事の量は自分で調節できるし、したがってほぼ定時に帰れるし。何も苦しゅうないのである。好きな勉強もでき、また勉強せずに酒飲んで映画観て、とか適当な新書読んで、21時に寝る、とかもやり放題なのだ。本当に大きなヘマさえしなければ今の職場にい続けることができる。年収も本当に少しずつだが、上がって行く。
しかし、高橋さんにしてみれば、「それで、安定しているからなんだっていうの?どうせ死ぬだけなのに」という感じだろう。うむ。そうだよなあ。不安定さを逃れたくて、就職したのに、そして一応うまく行ったのに贅沢な話だが、安定してみると、「だから何なんだ?」とは正直思うんだよな。
大学院生時代は「自立したい」と「それにはお金が必要だ」の二つの間でひたすらに苦しんでいた気がする。「自立したい」という気持ちに勝つ欲求は当時はなくて(今もかな)、とにかく就職することにしたのだった。就職活動をする中で、体育会系のカルチャーが片鱗でも見えるような場所は心理的に耐えきれないな、と思い今の職場を選んだ。
一つ一つは合理的な選択の積み重ねなのだが、それがものすごく無難なところにたどりついて、では、それでいいのかと感じなくもないこの頃である。教える仕事なんて学生時代からやっていたことで、できることは目に見えていたし、あんまりガツガツとした進学校や部活重視の学校だと休日がなくなって大変だから、そうでなさそうなところを選んだ。それで実際そのとおりのところに就職できた。予想通りそつなく仕事をこなせている。
つまり、全て希望通りなのだ。その上でなんだかモヤモヤするのは、結局自分の幅が広がっていないなということである。随分と早々と、おさまるべきところにおさまってしまった。「それで、安定しているからなんだっていうの?どうせ死ぬだけなのに」と高橋さんに面と向かって言われたら、どうしよう。
大学時代に気づいた自分の長所は、周囲の状況から手に入れることが可能なものを見定め、それを手に入れるという能力である。「手に入らないものは最初から求めない。できないことはしない」というのとは違う。手に入らなさそうなものを求めるときは、安心してそれを求めることができるような環境整備をまず先にやる。そのように何事も、ステップに区切ってやろうとする私なのである。
その結果として、丸腰でラスボスに向かう、みたいなことはなくなってしまった。大きな困難に歯を食いしばって立ち向かううちに、いつの間にか大きく伸びていた、というような受験のサクセスストーリーのような可能性は、ここ五・六年の私にはない。
でも、そんな風に常に計画立てて、先を見通して、今にある程度余裕ができるような進み行きをおこなうようにして、それで、どうだっていうのだろう、
と思わなくもないなと感じるのである。
***
余談なのですが、この土日月と私は三連休で、どっかに行ったりすればいいもののずっと喫茶店か図書館にいて喫茶店・図書館・自宅をぐるぐるしているばかりであり、誰とも一言も会話しなかったので、インタビュー企画で友人と話すときに会話ができなくなっていて自分に引きました。
(私)「祖母の家が八王子にあるんですけど」「八王子なんだ」「いや八王子というか、豊田なんですけど、ちょっと八王子方面なので八王子が出ちゃいました」とか、「通信でいま**免許とろうとしているんだよね」(私)「そうなんですね。何時間くらいですか」「40時間です」「40時間ですよね」「あれ知ってるの?」「いや、40時間と言われたので、そうですよね、という気持ちをこめて」
とか、もうなんだか、相手の発した言葉をどういう風に受けて次の会話につなげるのかわからなくなっていてそれを弁明して、弁明中にまた新たな言い間違いをして、の繰り返し。
私が最高のツイッターだった頃
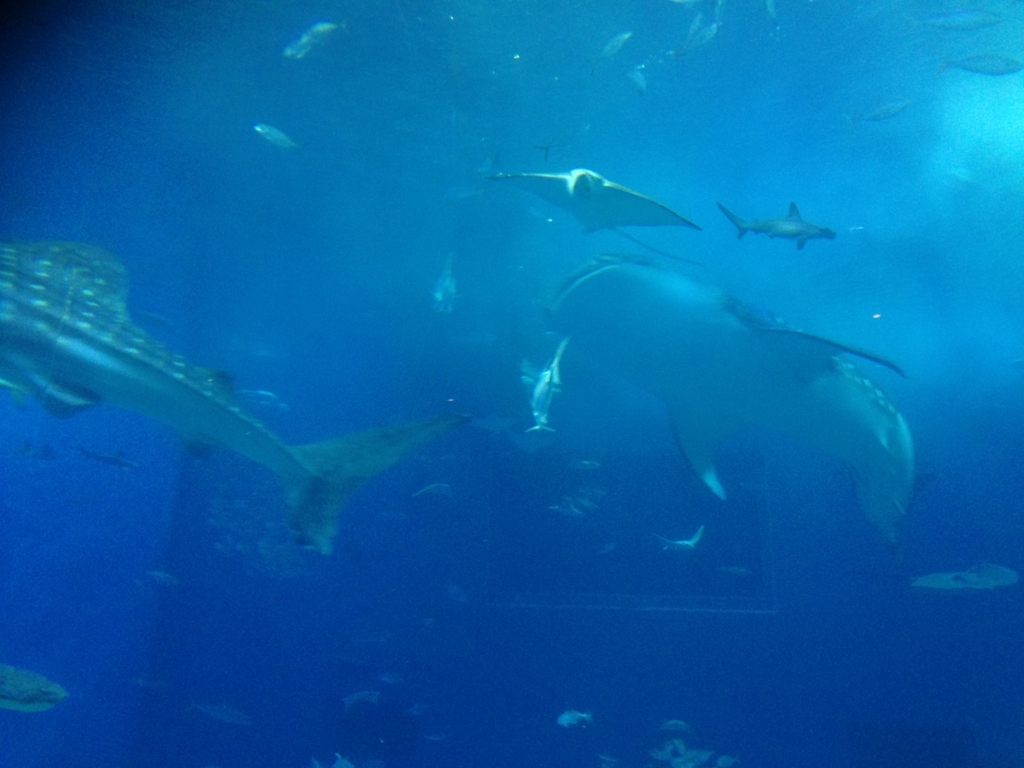
最近ちょっと真面目な記事ばかり書いていたので、今日は私が最高のツイッターだった頃の話と、その少し後までの話をします。
ツイッターって知ってる?
私がツイッターを始めたのは、大学一年生の6月ごろです。駒場の食堂で、浪人した私よりも一年先に入学した高校時代の同級生から、唐突に勧められたのでした。
「ツイッター…?そういうのがあるのは知ってるけど、なんだか難しそうだし、私はやったことないかも…」
こんな感じままのピュアな受け答えをして困惑を隠さない私に、彼はたたみかけました。
「いやいや簡単だよ。みんないるからやってみなよ」
手際よく私からGメールアドレスを聞き出した彼は、ものの3分ほどでアカウントを作ってしまったのでした。
以降、私は3年以上astro_cat_という名前でつぶやき続けました。多い日は1日に50もつぶやいたと思います。一週間に15コマくらいとっていた、せわしない日々。私は暇さえあれば人差し指でTLを下に引っ張っていました。
一応エクセルに、当時のつぶやきの数々を保存しています。私は一つのつぶやきの文字数が多めだったので、1万2千ほどのツイートの文字数は合わせて60万を超えています。その大半はほんとうにクソofクソなのでもはや頭から読み返すことなど思いもよらない状況です。
それは私という人間の記録としては意味があるかもしれませんが、私に興味を持たない人々にとってはただのゴミの山です。よくもこんなものを、大衆の目に映りうる形で発信していたものだなと感心します。
私がUTクラスタだった頃
ツイッターを始めてしばらく、私は「UTクラスタ」の一員となっていました。
UTクラスタとは何か。要するに主に前期教養課程の東大生ツイッタラーたちの総称です。
「前期教養課程」と決めつけてしまいましたが、「UTクラスタ」という言葉で後期課程、大学院生を含めた東大生ツイッタラー全体を示すこともあるとは思います。というか、そちらの方が正しい言葉の使い方かもしれません。
しかし、私はここで、主に前期課程の東大生ツイッタラーの集合体を示して使おうと思います。なぜなら、後期課程以降はそれぞれが専門の勉強を始めるため、皆一斉に進振り(進学先の科類決定のための手続き。成績が良いと選択肢が広がる)の方向に向けて勉強していた前期課程の時ほどに、帰属意識を持ったカテゴリとして「UTクラスタ」という名前が用いられることはなくなるからです。少なくとも、私自身はそうでした。
そのこともあって、後期課程や大学院生になってまで、「UTクラスタ」云々言っている人はださいな、と後期課程に進んだばかりの私は思っていました。私にとって、「UTクラスタ」とはどこまでも前期課程と結びつくものなのです。なので、ここではその私の感覚を大事にしてこの言葉を用いたいと思います。
さて、話を最初のところに戻します。食堂で友人に勧められ、ツイッターを始めた私は、大半の平々凡々なUTツイッタラー達と同様のステップを踏んで、ツイッターという場に自分を順応させていきます。
今、全つぶやきを保存した膨大なエクセルファイルの最初の部分を見ると、ツイッターを始めた直後、私は「Twitterはじめました。よろしく」「なにつぶやければいいかよくわかんない」的なつぶやきをしていることがわかります。
見ての通りツイッター初心者の大半が一度はつぶやくのではないかと思われるような完全にテンプレに則ったつぶやきです。もちろん、テンプレだと思ってやっていたわけではないのですが、後から振り返ればテンプレに綺麗に乗っていました。
それから二週間くらいはTLを現実の延長と捉え、自分の中で特定している中堅ツイッタラーの友人(フォロワー200くらい)に突然「そうかな?」とかリプライを送って周囲を困惑させたりしていました。
もう少し後になると、要領がわかってきて同じ類(たぐい)の人っぽいUTツイッタラーを積極的にフォローし、クラスタ内で通貨となる「英一つまんなすぎ」「試験終わったらオンキャン焼くわw」的なネタをつぶやくようになります。
普通に授業に間に合ってるにもかかわらず、教室内で「ぶっち(寝過ごすなど、よろしくない理由から授業に出ないこと)だわ、これで3度目w」とかつぶやき、ファボ(お気に入り登録)をもらったりしたこともありました。あの時にもらったファボは嬉しかったなあ。一時期ファボをもらうことが快感になっていました。
こうして述べていると顔から火が出そうになるのですが、要するに私はちょっと自意識過剰な普通の大学生がやることを普通にやっていました。
「オンキャンパス意外といいよね」とはちょっと言えない
私が授業に間に合いながら「ぶっち」とつぶやいていたように「試験終わったらオンキャン(当時の1年前期の英語の教科書)焼くわw」とつぶやいていた当時のUTクラスタたちの大半は、今も大切に『オンキャンパス』を持っているのではないかと思います。別につぶやきの内容が現実かどうかということはどうでもよかったのです。
ちなみに、脱線しますが、私は『オンキャンパス』と『キャンパスワイド』(こっちは当時の1年後期の英語の教科書)を二冊ずつ持っています。TL上ではいざしらず、現実の私はオンキャンパスが結構好きだったのでした。私の友人には『オンキャンパス』のリスニング教材を子守唄がわりに聞いている人もいました。
『オンキャンパス』と『キャンパスワイド』について詳しく知りたい方は以下を参照してください。英語力を高めたい人にはおすすめです。
今少し考えてみて思うのは、反抗期を抜けきらない19歳前後の私たちにとって、『オンキャンパス』は母親のようなものだったのかもしれないな、ということです。高校生男子が「お母さん大好き」とは死んでも言わないように、UTツイッタラーの自認を持っていた私は、オンキャンパス焚書オフ構想すら膨らんでいたUTクラスタのTLの中で、「オンキャンパスって実はとてもいい教材だよね。」というようなイカ東発言は死んでもできないなと感じていました。一気に場が白けてしまいます。(ところでイカ東ってもはや死語ですかね)
俺らマジ、最高のツイッターだわ…。
話を戻しましょう。建前と本音が全く異なること。そんなこと、みんなわかっています。わかっていながらやっているのです。私たちは、単に試験が近づいてきたことの興奮と不安を分かち合いたいだけでした。だから、その目的に合わせて現実を改変することをいとわなかったのです。
そうだ、試験勉強を前日に始めたことにしよう、どうせ誰もその真偽なんて確かめないのだ。それで盛り上がるなら、いいじゃないか…。
どうやったらさらに盛り上げることができるか、ということを、駒場図書館で眠い目こすって必死に試験勉強をしながら、私は考えていました。あの、そこに座るものを常に眠くさせる、ぶよぶよとした不気味なクッションの椅子に座って。
ガリガリ勉強しては、「やばい」「勉強してない」とつぶやきます。すると、ファボが来るかどうかは別として、私のつぶやきに呼応するように誰かが「英一だるい」とつぶやいたりします。それを、私はファボをもってむかえます。「俺らマジ、最高のツイッターだわ…。」そんなことを思いながら。
UTクラスタからの離脱
前期教養を終えると、「英一」「オンキャン」などの共通言語が失効し、個々のツイッタラーは、進振りで決まった進学先のクラスタに自分を合わせていこうとするとともに、前期教養時代のクラスタから自己を差別化し始めます。
eeicのように後期課程でもまた前期課程の祭りを繰り返しつづけるクラスタを形成するところもあるのですが、私の所属した後期教養はそうではない方でした。そもそも、後期教養とは「試験終わったらオンキャン焼くわw」的なノリを前期時代から、何か汚いものでも見るように見ていた人たちの集合体であったのです。
そういうところに所属するようになったことと軌を一にして、私も前期のUTクラスタのノリからは卒業していきました。
しかしそれは私がeeicとか「オンキャン焼くわw」よりも高尚になっていったということではもちろんなく、また別のノリが通貨となる共同体に参入していったということです。
離脱後の私とツイッター
UTクラスタから足を洗いはじめたこの時期くらいに、私は、友人の影響もあって、ツイッター上に巣食うネタツイッタラー(?)を数人フォローし始めました。
また同時に、ツイッター論客の発言も盛んに観察するようになりました。
前者は「ネタ」とだけ聞くと軽そうですが、誰でもわかるようなネタにわかる人だけわかるネタを巧妙に織り交ぜ、それを当意即妙に投下することで日々「面白」を生み出すことのできるような才気溢れるユーザー達であり、私の中では「詩人」に分類されるべき面々であります。
「あぁ、こういう才能のある人たちが、現実世界では普通にサラリーマンとかフリーターとかやっているんだ、すごいな、この才能の蕩尽は。贅沢だな。これを読んでいる私…。」
とかそういうようなことを思いながら継続的に私は、彼らを観察していきました。
後者はツイッターで青筋立てて議論する人たちであり、ニュースなどで話題になる事柄について時宜をえた賢い発言をして300RTくらいは比較的容易に稼ぎだす人たちです。
彼らのやりとりを見て、議論に強いというのはこういうことをいうのだ、と感心するとともに、「議論に勝つための議論」の浅はかさも学びました。
そしてまた、その浅はかな「議論に勝つための議論」ですらまだ議論しようとしているだけましなのだな、と思わせてくるような有象無象の「そもそも議論しないクソリプアカウント」の存在も知りました。インターネットって怖いな、と思いました。
UTクラスタを離脱した私は、その後もツイッターをやり続けました。そうして、時折寂しくなると、ふと在りし日のUTツイッタラー達のアカウントに立ち戻り、前期教養時代の「最高のツイッター」だった私たちを懐古的に振り返ったりしたのでした。
===
学生生活について正面から書いている記事は少ないのですが、のちに一つだけ以下の記事を書きました。よろしければどうぞ。
学校の物語を語る欲望:「東大合格者数高校ランキング」に思う
ツイッターを見ていたら、東大合格者に言及するつぶやきがあったので、高校時代たまに見ていた「高校ランキング」スレッドを少し読んだ。
懐かしい。当時の熱気そのままである。いや、むしろ加熱しているか。
「どこそこの高校が躍進し、有名なあの高校が凋落。これなら公立トップと同レベル。しかし医学部は増えている。医学部だけ見れば、負けてはいない…」
進学実績をもとに学校の格付けがなされ、憶測が飛ぶ。くだらないと一言で切り捨てることは簡単だが、実際このような言説の場に反映される多数の色眼鏡が社会で効力を持ってしまったりするものだから、完全に捨て去ろうとする態度も、それはそれで何らかのコンプレックスのようにとらえられてしまう。
こういったスレッドの伸び方ときたら異様で、東大の合格発表日である3月10日だけで、3000スレッドほど動いている。
これを見ながら、なぜ東大合格者数の多い高校について語りたいという欲望が生じるのかと素朴に思ったので、少し考えてみる。
最近、有名進学校に関する新書を目にする機会がよくある。そういう新書が統計的に増えているかは調べていないのでわからないのだが、本屋ではよく目にする気がする。どこそこの高校の教育方針が素晴らしい、この高校で育った子はこのような性質を帯びる、など。
それを時たま手に取り、思うのは、そこに書かれていることがその学校独自の物語であるということだ。
物語とはいえ、この物語は完全なる空想ではない。物語られる学校内の生徒にとって、それはまさに自分の所属している世界の出来事であり、それがフィクションであるとしても、繰り返し吹き込まれるうちに自分のアイデンティティに少なからず影響を与えるものとしてある。
受験生にとっては、それは勉強の末に到達できるかもしれない世界の話であり、学校の物語を好む大人たちにとっては、ある日その学校という物語世界の住人が、新人として入ってくるかもしれない、もしくは自分の遥か上の上司がかつてそこに所属していた過去が明らかになるかもしれない、そのような、現実と陸続きの物語としてある。
学校を語ることは、今ある現実とは別の、しかし現実と陸続きになった、もう一つの現実を語ることの欲望である。
だから、学校の先生とは何よりもまず、物語の世界の演出者であり、役者であるのだろうと思う。
もちろん、この話は学校に限らない。会社にだって物語は必要だ。個々の家庭にもそれは必要とされる。
蛇足だが五年ほど前、僕は、遠い親戚から、自分のルーツが和歌山県にあり、僕の江戸時代の先祖は廻船問屋をやっていたと聞いた。
廻船問屋!
あの教科書に載っている、菱垣廻船や樽廻船を所有して、西回り航路や東回り航路からやってくる船より水揚げされる海産物を、僕の先祖は上方に送ったりしていたのだろうか…そんな風に想像して、僕はその想像に陶酔するような気分であった。
余白から生まれる透明な寂しさがいい 市川春子『宝石の国』
大学一年生の時、シラバスでふと見つけた船曳ゼミに未だに参加しています。その読書会で市川春子『宝石の国』を読んだので、今日はその感想を書いていこうと思います。
※この読書会の関連で読んだ作品について考えたことをまとめた記事として、他に以下のものがあるので、よろしければこれらもご笑覧ください。
余白の多い画面が良い
正直一巻の半ばまであまり惹きつけられる感じはなかったのだが、それをすぎたあたりからこの作品の描線に感覚が馴れていき、容易に抜け出せなくなってしまった。
先に言ってしまうが、ストーリーラインの中に見るべきものは正直ほとんどないと思う。SF、ファンタジー、仏教のモチーフが入り乱れる本作の設定は悪く言えばめちゃくちゃ。よく言えば自由。入り乱れているそれぞれの要素がうまく絡み合えば「めちゃくちゃ」ではなくなるのだが、正直個々の要素があまり巧みに結びついていない感じがある。
それでは何がいいかというと、多くのものを捨て去り、綺麗で清潔なものを残す、作者の感性、世界の捉え方がよいのである。ストーリーラインは、この作者の世界の捉え方を示すための手段にすぎないように思われる。
まず1コマ取り出してみよう。以下のような画なのだが、要するに描かれる対象が丸みを帯びた線により抽象化されており、複雑な部分や汚れは捨象されている。作者は描写を行う上で厄介なものを無視しているのである。

厄介なものが捨てられた、綺麗な身体
同様の操作は彼らの身体に関する設定の上でも行われている。主人公たちは「宝石」であるとされ、作中の大部分でピカピカと光り輝いており(下図参照)、破壊されても輝く宝石の破片になるわけで、血液が飛び散ったり身体の形が不恰好に変わったりすることはない。痛みの感覚もないし、性別もないのだ。身体の持つナマモノ故の厄介さが、ここでも徹底して無視されている。

それゆえに、第一に私が持つことになったのは「なんだか宝石いいな、綺麗で…」という偏差値ゼロメートル地点の感想だった。第二に持つことになったのは寂しい、物悲しい、という感想である。前者は後者と結びついている。多くのものを捨象することからくる寂しさが、小さな宝石の輝きを強調しているからだ。
捨てることが喚起する、透明な寂しさ
それでは、多くのものを捨象することがなぜ寂しさを喚起するのだろうか。
それは、読み手の想像力がその裏に捨てられてしまったものを二重写しにして読むからだろう。抽象化された描線は、ずれ、重ね書き等を排した迷いのない曲線で構成されており、線と線の間は多くの要素を捨象したがゆえに成立する単色の広い余白で構成されている。読者として僕はここに、本来あるべきものの影を見、そしてそれが捨て去られることの寂しさを感じるのである。
同様の余白は、ストーリーの上では、時間的・空間的なものとして現れてくる。敵との戦いと日常生活との単調な繰り返しからなる展開らしい展開が不在のストーリーラインにおいて、目を引くのは彼らが作品内で経る時間の長さ(エピソードとエピソードとの間に100年くらいの時間が経過していたりする)や、彼らせいぜい二十数人が活動する場としてはあまりに広い草原である(下図参照)。

ここで注目されるのはやはり余白であろう。描出されたエピソードが彼らの単調な生活のほんの一部であることを示すかのように挿入される間に過ぎた時間の長さへの言及は、描かれることのなかった時間=余白を読むものに意識させる。小さな宝石たちと大きな草原との対比は、その間にある広大な空間に広がる何もなさ=余白を強調する。
「なんだか、とてもいいな」と思ってしまう寂しさ
大きなものと小さなものを対比した時、そこには透明な寂しさが生まれてくることを、柴幸男『わが星』が岸田國士戯曲賞を受賞した際に、選考委員である野田秀樹が指摘したが、この作品ではまさに大きなものと小さなものとがいたるところで対比されており、それこそが、作品全体を覆う物悲しさを生み出しているように思うのである。
多くの人がこの作品の描写の上での余白に、また、この作品が前提とする時間的スケールの大きさと、クローズアップされるもののちっぽけさとの間に生まれる余白に、不思議とひきつけられてしまうのではないかと思う。それは目に入るあらゆるものに関して容易に情報を得ることができ、また時には情報を得ることを駆り立てられる今日においてこそ一層力を増す、描かないこと、捨てることの魅力なのだと思う。
===
こちらもどうぞ
こち亀はどこで間違ったのか

こち亀の「くそ」化
別にアンチを助長するわけでは決してないのだが、数年前以下に紹介されているスレを見つけて、スレタイトルから驚かされたのを思い出す。
このスレタイトルがいかなる背景から登場するにいたったかということに関しては、以下の解説が参考になる。
解説
【こち亀】
こちら葛飾区亀有公園前派出所。作者は秋本治。1976年より週刊少年ジャンプにて連載開始、現在も連載中。
東京の下町・葛飾区の亀有公園前派出所を舞台に、破天荒な主人公の警官・両津勘吉が巻き起こす数々の騒動とそれらに彩りを添える多数の個性豊かなサブキャラクターの活躍を描いた痛快ギャグ漫画である。
初期はただの職務怠慢バイオレンスポリスマンだった両津だが、連載を重ねる毎に作者の画力の変化で丸みを帯びそれとともに圭角が取れた下町人情オヤジの要素が付加されていった。連載が軌道に乗った中期以降も、秋本治の緻密な取材とそれを活用する構成力、背景にまで細やかに気を遣う丹念さ、実験的で革新的なアイディアを武器に ジャンプ黄金期にあっても同作品は白眉であった。しかし、後期から現在に至り、女性キャラの奇乳化、女性新キャラの乱発無意味なロリキャラの登場、古参キャラの自我崩壊、起承転結を無視したストーリー、稚拙で場にそぐわないモブ・背景、少女漫画の描写を折衷させたが如き拙い筆致で連載を続け、無様な姿を晒す。同時に、両津は下町パワフル人情お巡りさんから 生意気娘のいる寿司屋の住み込み職人に転職。敬愛する春日八郎も忘却の彼方、脂の乗り切った30ぐらいの粋な女
(48巻/おにあいカップル!?の巻)が好みだったはずだが、今や単なるロリコン少女萌えオヤジとなりさがる。くそら糞飾区糞有糞園前糞出所【こち亀】Ver.51(レス5番より)
つまり「後期」におけるこち亀の変化を許すことのできない読者達が、現在のこち亀のあり様を貶すために用いられる言葉が「くそ」であるわけである。
私自身は、長大なこち亀のすべてをカバーしているとはとても言えず、小学生の頃に中心的に読んだのは80~120だが、奇しくもこのあたりがこち亀の「後期」への移行期間であった。幼い私にも、「奇乳化」は目についた。もともとヒロインの胸はそれなりに大きく描かれていたのだがそれが巻を追うごとにいや増しになっていき、120巻ほどでピークを迎える。
流行に聡く、凝り性の秋本氏のことだから、「今、女性の身体のデフォルメが来ている!」ということを90年代前半くらい(90巻台後半)に察知しそれに合わせていったのだろう。
その認識自体は間違ってはいなかったのだろうが、まあ、あまりよい方向性ではなかったと思う。私は80巻台に一つの完成を見るような作者の下町への眼差しをこそこち亀の本領と捉えているからだ。
作者の下町への眼差し
「作者の下町への眼差し」とはどういうことか。
80巻台のこち亀を読むと、街並みを描写することに力が割かれているのがわかる。ストーリー上は必要ないような余りのコマに、ふと通りの一角が丹念に描きこまれていたりする。
他のジャンプ漫画にこのような余りのコマはほとんどないといってよいだろう。通常どのコマも、何らかのキャラクタの動きや、ストーリー進行上不可欠な事物を描き出している。
余りのコマに現れるしばしば異様なまでに力の入った下町描写は、漫画の企図が破天荒な警官両津勘吉の行動の描き出しにあるのではなく、その行動に焦点化することを通し、そのような行動が行われる街自体を描くことにあることを示していると考えられる。
つまり80巻台のこち亀のコマは、それを描き出す作者が下町をどう見るのかという眼差しの物語でもあるのである。両津勘吉は、下町の風俗を描き出すきっかけとして機能している。
私にとって80巻台のこち亀が面白かったのは、両津勘吉のキャラクタ造形に加えて、この作者の街並みへの眼差しだった。自分が下町を歩いたとしたら簡単に見落としてしまうであろう何の変哲も無い通りをあくまで丹念に描き出すことにより、そこに作者が感得している一種の情味が、読む私にもうつってくる。下町をみる見方というものを、私はこち亀から教わった気がするのである。
だから、それが明らかに変化していく110巻以降を読むことは私に取って実りの多いものではなかった。上に引用した解説のうち、以下の部分は思わず頷いてしまう。
後期から現在に至り、女性キャラの奇乳化、女性新キャラの乱発無意味なロリキャラの登場、古参キャラの自我崩壊、起承転結を無視したストーリー、稚拙で場にそぐわないモブ・背景、少女漫画の描写を折衷させたが如き拙い筆致で連載を続け、無様な姿を晒す。同時に、両津は下町パワフル人情お巡りさんから 生意気娘のいる寿司屋の住み込み職人に転職。
そう、110巻〜120巻台に顕在化した秋本の新路線は私には迷走にしか見えなかったのだ。
こち亀はどこで間違ったのか
120巻以降もたまに古本屋でこち亀を立ち読みすることはあったが、それらの新路線が効いてきているようには思われなかった。路線転換期の「稚拙」さが改めて作家としての新しい境地を開くことに期待を抱いてはいたのだが…。
やはり、こち亀の本領は下町の風俗描写であろう。もちろん、秋本は以降も折に触れてそれに立ち戻りはしていた。しかし120巻台以降の下町描写は過度な情味を読者に押し付けるようなものであり、正直、鬱陶しくて仕方がなかった。80巻台に見られたような冷静な観察者に徹する作者ではなく、「これが下町だ、どうだ?いいだろう?」と盛んにせまる推しの強い作者がそこにいた。下町への新たな見方をそっと差し出してくれるのではなしに、自分の見方こそが下町の見方なのだと強要してきた。しようがない。どうせ、何を書いても打ち切りになることはなかったのだろうから。
===
ジャンプ漫画についてはこちらもどうぞ
ヒカルが碁に向かう姿のリアリティ:ジャンプ的成長物語の傑作『ヒカルの碁』

先週末に実家に帰って、ふと『ヒカルの碁』を読んだ。
主人公が成長していく様を描いたジャンプ漫画として、この作品はジャンプ史上最高傑作と呼んでいいんじゃないかなと思う。題名で「碁」と名打っているが、この漫画は碁の漫画ではなく思春期の少年の成長物語だと私は考えている。
ちなみに:最近二年くらいの時を経て、改めて囲碁について考えましたのでもしよろしければこっちも併せてご笑覧ください。
ヒカルが碁に向かうまでの描写が丁寧
この漫画は、囲碁にのめり込んで行くまでのヒカルの心理的過程を、実に丁寧に描き出している。何しろヒカルが自発的に囲碁に向かうまで、単行本で4冊くらいある。主人公がスポーツなりゲームなり料理なり、何かに打ち込むジャンプ漫画は多くあるが、打ち込むまでの過程をこれだけ長く書く漫画は他にないのではないだろうか。
おそらく囲碁というジャンプ読者の大多数にとって馴染みの薄い題材を選択したがために、例えばサッカー漫画等であるように「ライバルへの対抗意識」とか「弱い自分を克服するため」とかそういう単純な動機で主人公を囲碁に向かわすことは難しいと原作者は判断したのだろう。
ヒカルが碁に打ち込むことになるまでの過程には、思春期の少年が抱える問題がいくつも登場する。例えば外から見られる自分(=佐為のいう通りに打ったことでほぼ最強近いパフォーマンスを出してしまい、強豪に追われる立場になった自分)と実際の自分(=碁など全く知らないし、自信を持てる技能を持たない自分)との乖離。また、打ち込む対象を見つけられない根無し草的なありように対する葛藤など。
これらの問題に悩むヒカルの姿には共感できるし、それらと対峙する中で碁に向かって行く動機も納得できる。だから碁など全く知らない私のような大多数の読者も、「囲碁よくわかんない。読むのやめよう」とは決してならないのである。むしろ碁に向かうヒカルの心理的過程を追うことで、ヒカルというキャラクター、そして佐為にどんどん惹きつけられて行く。自然と、碁にも関心が高まってくる。
佐為の暴力
ところで、今回改めて読み直して思ったのだが、この作品はなかなかシリアスなテーマも扱っている。それは佐為の暴力である。
佐為はヒカル以前に江戸時代の囲碁の達人本因坊秀策に取り憑いていたということになっている。秀策は彼自身相当の腕前を持っていたが、佐為が取り憑いて以降、秀策は佐為の指示する通りの碁を打つようになった。そして、秀策は佐為の強さにより名声を獲得する。
佐為は碁がもっと打ちたい、さらなる高みに到達したいという一心で、秀策に自分の碁を打たせるわけだが、このようにして秀策を自分の身代わりのように扱ったことの暴力性について、佐為が気づくのは、逆に今世で自分がヒカルに取り憑いた理由が、ヒカルの成長のためだったのではないかということに思い当たってからである。ヒカルは佐為のもとでメキメキ力をつけ、途中から佐為にあまり打たせなくなる。それを横目に見て、佐為は自分がヒカルに取り憑くことになった理由に思いをめぐらしたのだった。
何かのために利用される側に立って初めて、自分もまた人を自分のために利用してきたことの暴力性に気付く、とまあ、こう書いてしまうといかにも凡庸なテーマだが、むしろ着目すべきは、この暴力性が、全く清算されずに終わるところであるだろう。
碁に殉死する存在としての棋士
作品終結部で人のために碁を打ち、人のために生きるということが、「遠い過去と未来を繋ぐ存在としての棋士」というテーマに回収されていく。棋士という存在の役割、運命が長大な時間的スパンの中の一部を継ぐことに求められ、秀策や佐為の死を意識するならば、棋士は碁という文化のために殉死するものと位置付けられている。
それでは、成長物語の主人公であるヒカルもまた、碁に殉死する存在としての位置付けを免れ得ないのだろうか。
このことを考える上で注目するべきと思われるのは、佐為の消失後にヒカルが秀策の棋譜を見て改めて佐為の強さに気づき、慟哭する場面だろう。
過剰なヒカルの泣き顔
今回読み直して思ったのだが、ヒカルが慟哭するこの場面は描き方として相当に奇妙である。まず作中でここほどヒカルの顔しか書かれなかった数ページはないだろう。しかも、モノローグ(というか、独り言)もなんだか性急である。あまりよく覚えていないのだが、記憶だけで述べると以下のような形だった。
自分が強くなったことで、佐為の強さが初めて理解できた
→もっとあいつに打たせてやればよかった。
→俺なんかじゃなくて、あいつが打つべきだった
このような思考の流れがヒカル自身によって語られそれぞれのコマではこれ以上ないほどに、読者のショタ心を刺激するようなヒカルの泣き顔、落ち込み顔が強調される。この辺りは読んでいて申し訳なくなってくる。いたいけな少年の泣き顔をこれほどあらわに、それも1ページのほとんど全てのコマにアップで映されると、一種の過剰さを感じてしまうのだ。本来それほどジロジロ見てよいものではないものを、コマに従えば信じられないほど何度も、それも正面から見ざるを得ない。
このシーンは、ヒカルの改心をこれでもかというほどに強調するために挿入されている。ここでヒカルは、自分のために碁を打つことよりも、自分よりはるかに神の一手に近い存在に碁を打たせることの方が、碁全体の発展に寄与するという観点から佐為に打たせるべきだったと言っているのである(もちろん、心の支えになっていた佐為との急な別れを受け入れられずに、戻って来て欲しい一心でそう言っている、という側面もあるのだが)。
こういった個に対する全体を優先させる思想は、やはり個に対する暴力性を孕む。佐為自体はヒカルの独創的な手を横で面白がり、後押しするような温かな支援者であったりしもしたのだが、敗者を排除するような勝負の世界の過酷さは、やはりより優れたものを是とするような思想にヒカルを置いていく。このような暴力性こそが囲碁という共同体を成立させる一つの掛け金なのだということを作品は第一に述べているように思われる。
そこでは棋士はあくまで、過去と未来をつなぐための多くの駒のうちの一つにすぎず、過去から未来へとつながる、そのつながり全体こそが優位に置かれているのだ。
しかし他方で、消えかかる佐為がヒカルに対し、「楽しかった」と言おうとしたように、神の一手から程遠いところにあるような、目の前の一手を元にしたヒカルと佐為との関係のありようにもまた、固有の意味がある。「過去と未来をつなぐ存在としての棋士」のいま・ここ性がいかに描き出されているかということが、この漫画の成否をわけるポイントなのではないか。
ヒカルの身体の描出
そこで見るべきなのは、おそらく思春期にあるヒカルの身体の描写なのだろう。ヒカルの少年らしい肢体の様々な動きは作中で生き生きと描き出されており、身体を持たない霊的存在である佐為とは対照的である。囲碁というと青白い痩せた少年をイメージしがちなのだが、小麦色に日焼けし、前髪部分を金に染め、ジャージを着込むヒカルは普通に運動部の少年っぽい。なんなのだろう、このギャップは。
今日は疲れたので、続きはまた今度書きます。
物語を読めないと死ぬ Jホラー映画の論理と『リング』

物語ることで生きる
人は生きる中で、自分の人生の物語を措定する。本当は大部分偶然が重なって、たまたま今のような自己があり、またこれからも同様に大部分偶然の作用によってこれからの生が形作られていくはずだが、それらの偶然に意味づけをすることにより、偶然の偶然性を捨象し、その人にとっての、なんらかの必然性を見出していく。
例えば、たまたま周囲に足が速い人がいなかったため学年で一番足が速い子がいたとする。その子が、「そういえば自分は子供のころからスポーツが好きだったし、得意だった。これからも足の速さに関しては誰にも負けない」などという物語を作ったとすれば、これは上で挙げたような偶然を必然性ととりかえ、自分の物語を作ったことに他ならない。誰もがこのように物語を作り、その物語に依拠して、現在の自己というものを確定している。
偶然培われた可能性も十分にある性向を、家庭環境に還元して物語ろうとすることなど、誰もがよくやるのではないか。例えば「うちは代々実業家気質で、みんな結構独立心旺盛なんだ」とか。また、偶然に出会われた出来事を自分のこれまでの行いに対する賞罰に還元したくなる人も多くいるだろう。突然の不幸に見舞われて、「これは身勝手な私に与えられた試練なのだ。」とか。
どの物語に関しても、「当たりだ」「外れだ」ということは実証的にはわからない。だから、「僕の人生の物語における語り手=僕の中ではそうしとこう」ということに過ぎないのだが、確からしい物語は他人の強い支持を受けることができたりもするので、ふと調子に乗って、それが自分の物語=フィクションに過ぎないことを忘れかけたりもする。
今年3月に出た千野帽子さんの本は、人と物語との関係について語った本であり、以上の事情もわかりやすくまとまっていた。
この本はweb連載をもとにしているので、内容の多くが以下から読める。
このように自分の人生を物語=フィクションとして捉えることは、人に迷惑をかけない限りは悪いことではない。それどころか、私はその人にとっての「その人の人生の物語」の虚構性を安易に暴くことは暴力的だとすら思っている。多かれ少なかれ、人は自分の作った物語に依拠して生きているのだから、いろんな人と一緒に生きていくということはその人の物語=フィクション=ウソの中に紛れ込んでいる、その人にとっての「本当のこと」を尊重することだからだ。…といって、できないことも多いのだけれど。
ホラー映画を観るのはなぜ?
そこで表題にあるホラー映画である。僕はとてもホラー映画が好きで、よく直近に見たホラー映画の話を同僚にしようとしたりするのだが、あまり芳しい反応をいただけたことがない。「観ないですか?」と聞いたりすると「私ホラー苦手なんです。怖いじゃないですか。グロテスクだし。」という返事が返ってきたりする。確かにその通りだ。怖い、グロい、可哀想、痛そう、悲しい。こう並べてみると、なんでこんなもの観るんだろうと思われて来る。しかし僕は観たい時は割と片っ端から観る。
「なぜ私はホラーを観るのが好きなだろう」−−−そんなことを時に考え、時に完全に忘れ、その問いとの関係においては不真面目な生活を送ったのち、先日たまたま映画『リング』を観返しながら、ピンときたことがあった。もちろん、それでホラー映画が好きな理由を言いつくせているわけではないが、しかし理由の一つを明らかにしている気がする。
そしてその理由は、上で述べたような、人が生きる中で、物語を語らざるを得ないことと関わっている。
ホラー映画の主題は、生前の物語を探すこと
『リング』は観たら一週間後に死ぬと言われる呪いのビデオを観てしまった女=浅川玲子の物語だ。玲子はその呪いを解くべく、元夫=高山竜司に協力を依頼し、二人で一週間の間に様々な画策をする。呪いのビデオに呪いをかけたのは誰なのか。そして、どうして。玲子らの必死の調べの中でそれらが明らかになっていく。
詳しいあらすじは以下を参照
『リング』を観返しながら、ホラー映画にしばしば現れる霊的存在への現世の人々による対抗は、その霊的存在の生前の物語を読み解くことによって行われるのだな、と気付かされた。
『リング』で呪いのビデオに呪われた玲子が取る手段は、呪いの背景を探り、その原因を断つことである。これは多くの幽霊譚と同様だ。生前思い残すところがあった者が死後霊的存在として猛威を振るうに至った場合、生者が取れるのは大抵、その者の鎮魂・供養であり、そのためには自分らに呪いをかけるものが何に対してどのような思いを抱き、今このように呪いを自分らにかけてきているのかを、その存在の認識に即して正確に読解しなければならない。
つまり、呪いを解き、猛威を振るう霊的存在を前にして生き延びることとは、その存在が呪いを開始するに至った物語を見つけることと不可分なのである。
『リング』という映画が秀逸なのは、この「物語を見つけなければ死ぬ」という呪いの根本原理を最後のどんでん返しにうまく利用していることだ。
物語を誤読すると死ぬ
玲子と竜司の調べで呪いをかけた存在は山村貞子という女と特定された。彼らは貞子の怒りを鎮め、呪いを解くために、貞子が呪いをかけるにいたった原因を特定した上で、貞子がいま、何をして欲しがっているのかということに関して推測する。そして、貞子の死体が眠っているとされる井戸の底に潜り、どぶさらいをしてその骨を見つけ、地上にもどしてやることで、呪いを解こうとする。
どぶさらいの最中、一週間後に死ぬ呪いをかけられた玲子が規定の時間を迎えたが、彼女は死ななかったため、彼らはこの方針が正しいことをいよいよ確信した。
しかし、その後、時間差でビデオを観た男の方は一週間後の時間を迎えて呪い殺され、女は自分たちの行為が結局呪いを解き得ていなかったことに気付かされる。つまり男は霊的存在=貞子の物語を読み違えたため、死ぬことになったのである。ここで、他人の物語の誤読は即、死に直結している。
ホラー映画では多かれ少なかれ、超人間的・超道徳的な霊的存在(『リング』では山村貞子)が現れ、破壊的な暴力を生身の人間に対して振るう。ひ弱な現世の人間たち(『リング』では上述浅川玲子や高山竜司)は力という点では決して彼らにかなわない。現世の人間は、彼らの生前の物語を発見し、正確に読解するしかない。霊的存在たちの実証的な事実だけ捉えても、彼らの呪いを解くことはできない。読むべきなのは、彼らにとっての、彼らの中での真実性である。それは、彼らの人生の物語=フィクションを読解することでもある。
このように、他人の物語の誤読が即、死に直結するという進み行きが、私にとってホラー映画が魅力的なものである理由なのだろう。なぜならそれは、物語を読むということの、もしかしたらわかりやすぎる効用を示しているからだ。つまり、至極単純にいえば、生き延びるために私たちはフィクションを読むのだ。ホラー映画というトポスでは、読解対象が霊的存在にとっての、彼らの中での真実、つまり一般的にいえばフィクション=虚構=「ウソ」のことも多いのだが、「ウソ」だからといっていい加減に読むことはできない。
ホラー映画は絶望的で残酷で、できれば目を背けたい描写が続く。しかし、誰一人生きのこらずに終わるホラーは稀である。むしろ、力の面では決してかなわない存在に現世のひ弱な人間たちが対抗しうるという結末は、私にとっては希望に溢れたものに思われる。それも、大きな暴力に対し、正面から同様の大きさの暴力を当てるのではなく、それ自体最も非力に思われる方法−−−すなわち、読むことによって。





